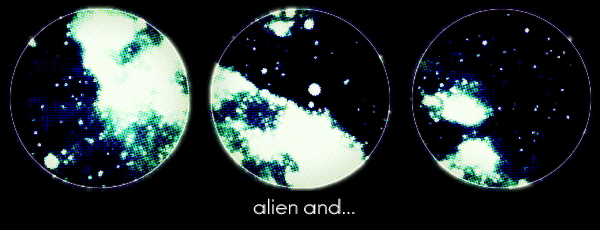 |
|
エイリアンも夢をみるのかしらんと、アーサーはなんとなくふいに思いつく。真っ暗な部屋のなか、眠らないの横顔を、テレビ画面の青い光が照らしている。エイリアンはその虹彩のない瞳で、じっと虚構のドラマに魅入っている。白い額から眉間へ至る稜線。 ふいに見られていたことに気づいてか、が視線を顔ごとアーサーに向けた。暗い部屋ではその瞳は、ますますもって底がない。 「どうかしましたか。」 「…いや。」 尋ねてきたのは穏やかな声音で、彼は思わず反射的に首を横に振る。そうですか、と不思議そうに少し瞬きをしたエイリアンは、再びテレビに顔を戻す。彼女が背中を預けるベッドの上では、アルフレッドが大の字になって眠っている。 ああもうまったく。いい大人が腹を出して。アーサーはほとほとあきれて、それでもやっぱりどこか優しい微苦笑でそうっとアルフレッドに毛布をかける。かつて自らの半神のように、かわいがったこども。知らないうちに大人になっていたこども。 深く考えることはよそう。アーサーは小さく首を振って、それから静かに、アルフレッドを起こさないようにベッドの縁に腰を下ろした。が夢中になって見つめている画面の中では、悲しげな青い目をした精悍な青年が、皮肉っぽい微笑みを美しくもどこか尊大な口端に浮かべている。『…実は高所恐怖症でね。』あらゆる感情がごちゃ混ぜになって、諦めと、絶望と、空虚と、それから?悲しさを押し隠すように、どことなく微かに、優しげでやわらかい冗談交じりの声だった。しばらくその黒い髪の男を見つめて、アーサーはああ、とふいに気が付いて声を上げた。 「ジュード・ロウの若い頃か!」 それにええとエイリアンがおかしげに言う。 「この頃から雰囲気あるでしょう?」 「ああ、すごいな…でもわからなかった。」 受け答えを返しながらテーブルの上に放り出されたDVDのジャケットに目を通す。ピッ、と小さく部屋のどこかで電子時計の鳴る音。午前1時。階下ではアルフレッドの両親が寝入っているので、テレビの音も、彼らの会話も、一番小さなボリュームで。 夜更かしをして、エイリアンに少し古い映画の話を聞いている。それってずいぶん、変わった話だ。けれどもこの地球に、ずいぶんな数のエイリアンが紛れ込んでいるそうだから、ひょっとしたら知らず知らずの内に、と出会う以前にもエイリアンと酒を飲んだり徹夜で騒いだり喧嘩したり泣いたり笑ったりしたことがあったのかもしれない。今までにであった人々の顔をぼんやり思い返しながら、アーサーは今までなら考えもしなかっただろう可能性についてなんとなくくすりと笑いだしたいような不思議さを覚える。 相変わらずの目は画面の上に釘付けで、おかしいな、今日はの自慢のDVDコレクションを鑑賞する会だったはずなのだが。映画はアーサーがシャワーを借りる間にもう4本目。ど派手なアクションシーンも宇宙人の侵略もない静かなスペース・オペラは、むしろアルフレッドの子守唄になってしまったらしい。確かに静かに、どこか哲学めいた映画で、彼のように途中から見ればそれがSFだとすら思わないかもしれない。 何分途中からだから、わからないな。 しかしエイリアンは一生懸命その何度目なのかも知らない映画に見入っていて、彼はくすりと先ほどとは違う苦笑する。ちっとも苦くない、年長者の微笑だ。しかたがないなぁ、って言いながら、それでも目が優しい類の。1世紀生きる女に、たかだか25歳の男が、なにをと彼は自分でもちょっと呆れる。呆れると同時に小さく欠伸が出た。今日は金曜日、一週間働きづめで、夕食からはしゃいでずっと映画を見ていた。さすがに疲れてきたようだ。 「眠いですか?」 とがちょっとわらう。 「ああ。さすがにな…でもお前、寝ないんだよなぁ。」 その言葉に、はちょっと謎めいた眉と口端の動かし方をしてみせた。 「寝ますよ?…その時が来ればね。」 ニヤリというその表情は、図らずも先ほど画面の中で見た微笑にどこか似てもいた。 ベッドはなにせアルフレッドのもので彼が占領しているし、アーサーはいつも寝床として提供されるソファに腰を映す。差し出された毛布を「悪いな、」と受け取り、半分だけ横になりながら首まで被る。エイリアンはテレビのボリュームをさらに下げた。どうせ台詞など覚えていると不敵な笑み。 アルフレッドの家に集まって帰るチャンスを逃してしまうと、アルフレッドがベッド、アーサーがソファで眠り、は決して眠らない。"昼寝"をする時は明るくないと、落ち着かなくって。そう言う。それが最近の常だった。アルフレッドの両親は、なかなか豪快で細かいことなど気にしないので、大の男二人と若い女の子一人がおんなじ部屋に泊まってもなにも言わない。変な勘繰りをする必要のないほど、三人があっけらかんとしすぎているのかもしれないけれど。近頃では、彼の家を借りると「あら、今日は泊って行かないの?」とまで言われる始末だ。アーサーの家はアルフレッドの家の隣なのだから、いつだってすぐに帰れるのだけどはそうはいかない。だからと言って、アルフレッドの部屋に一人残して帰るのは、なんとなく、アーサーには違うような許せないような、気がする。 眠らない。眠らないのではなく、彼女の長い長い半年がなかなか終わらないだけだ。そうしてそれは、アーサーやアルフレッド地球人の感覚で、それが彼女にとっては当たり前のことなのだ。 どうしてかしら、眠る準備を万全に整えた後なのに、なぜかな、眠気は停滞している。不思議に眠りにつく直前のふわふわした心地のまま、それでも彼の目は冴えていた。このままいつまでも、起きていられるような気がする。それはいつまでも生きていることと同義だろうか。いつまでも起きているというのは、いつまでも死なないというのと同じだろうか。いつまでも眠らなければ、いつまでも生きていられるかしらと、ふいに思う。 それから彼は、その思いつきとは違うことを、またテレビの画面に視線を戻したエイリアンに囁いた。 「…何日だっけな、」 「何がです?」 眠ってしまったアルフレッドを気遣ってか、眠ろうとしているアーサーに遠慮してか、うんと静かな声だった。頭の後ろ半分が眠っているような気分で、それでもアーサーはぱっちりと目を見開いてを横向きに見ていた。「が起きてる時間だよ。」 それにああ、とは急な話題にも慣れたように首を傾げた。 「地球時間で、1034日――約2.8年。」 すらすらとよどみのない答え。少し、ほんの少し自然に持ち上げられた口元。の目は、じっとテレビの青い光を見つめている。その横顔を、横向きに眺めながら、ふいにアーサーはいつか長いと思ったその時間を、短いと思っている自分に気が付く。 「たったそれだけかあ。」 普段ならばきっと言わないだろう。半分が眠ってしまった脳は、思いも寄らぬ動きをするものだ。自分の口が動くのすらも、どこか他人の夢のこと。ぱっちりと緑の目を開いたままのアーサーを見、それからは首を傾げた。その動作が、なんとなく彼女の微笑であることを彼は知っている。 「ええ。たったそれだけの間ですよ。」 「で、おんなじだけ寝るんだろ?…長いなあ。」 心の底から感心しているような、どこか残念そうな声音で、それがあまりに無邪気なので、エイリアンは笑みの代わりではなく首を傾げる。それでも少し、目が自然に微笑んでいた。 「ねみぃなあ…、」 地球人が半分眠っているような声音で呟く。 「眠ったらどうです。」 優しい穏やかな声はやはり抑揚がなく、聞き慣れない者には素っ気ない。 「………眠るのが、もったいない。」 気がする、と小さく語尾を重ねて、アーサーが耳まで赤くする。 「あなたがたは夜眠らなくては。」 「…ずっと起きてたいな。」 「それは我々にも不可能です。」 ふいに立ち上がってソファの傍らに腰を下ろすと、毛布の上からエイリアンがアーサーの肩をトン、トンと叩き始めた。異星人の癖に、子守歌のリズム。どうして知っているんだろうか。お得意の映画仕込みだろうか、それとも子守唄のリズムは、すべての宇宙で共通なのかしら。 心臓の音に似たリズムだな。 そう考えながら、ついに残り半分の脳みそも眠り始めるのをアーサーはぼんやり認識している。もう知り合って1年半以上になるエイリアン。もうあと1年半弱しか、起きていられないエイリアン。やっぱりその時が来たら、どんなに眠りたくないと思っても、いつの間にか朝が来ているように、彼女も眠ってしまうのかしら。そうして明日の朝、映画を観つづけたがアーサーとアルフレッドに当たり前の顔しておはようと言うように、約二.八年眠り続けて目覚めたエイリアンに、あったりまえの顔して自分はおはようと言えるだろうか。ああよく寝た、と目蓋を開いて朝日の中が背伸びをする、その時果たして彼女の体はこの星の上にあるだろうか。 未来のことなんて誰にもわからないな。 うつらうつら、エイリアンの子守唄のリズム。自分の幼い記憶にあるものと変わらない。 「眠りたくないなぁ…、」 ほとんど寝言のようにつぶやいたアーサーに、確かにが笑った気配がする。 「おやすみなさい、アーサーさん。」 また明日、とやわらかい声。 お前の明日は千と三十四日もあるくせに。文句を言おうとする舌がもつれて、ただのむにゃむにゃという意味の通じない寝言になった。それでもそれに、エイリアンはそうっと首を傾げる。 噫千と三十四日なんて、短すぎる。 ほんの少しの夜更かしで、もう少しだけ、側にいてくれよエイリアン。君だけはいつまでも、眠らないでいて。 |
(20120112)