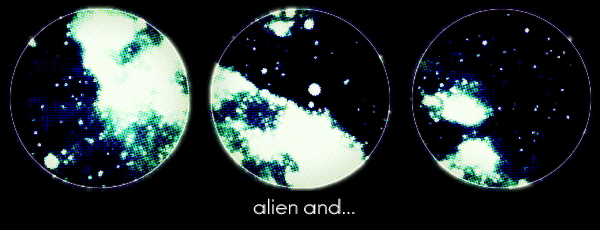 |
|
休日の朝、優雅な日曜日。特に予定もなく、かといって午後までゆっくり惰眠を貪るでもなく、アーサー・カークランドは庭の丸テーブルでひとり、英国式の朝食を決め込んでいる。のりの効いた白いシャツに、まっしろなカップとソーサー。彼自身が丹精込めた花の咲き乱れる庭で紅茶を飲む様子は、これで向かいに大きな映画女優の被るようなまるい帽子をかぶって空色のワンピースでも着た美人がいれば、今の100倍様になるだろう。 しかしながらぼっちなことを嘆いても詮無きこと。すっかりぼっちに慣れきっている彼は、それに疑問も気恥ずかしさも覚えず、ただ清々しい朝の空気と水を撒いたために匂い立つような緑、そしてその中にほのかに香る紅茶のやわらかな色にご満悦だ。静かな朝。特に予定はないし、積んだままにしていた本でも読もうか。昨日焼いたスコーンの残りも併せて、すっかり朝食を堪能している彼の耳に、ドタバタと騒々しい足音が聞こえ始めた。 「アアアアアァァサアアアアァァァァ!!!!」 いつになく切羽詰まった声で、その大きさにはうっかりアーサーがスコーンを喉に詰めかけるほどだ。紅茶をグイと喉に押し込んで、なんとかつっかえた黒い塊を嚥下する。息つく間もなく「どっ、どうした!?」と声を上げると、垣根を壊すように乗り越えながら、アルフレッドが隣家の庭に飛び込んでくる。 「アーサー○×△ちちんぷいぷい森の木陰でどんじゃらほい!!!」 「なっなんだって!?」 さっぱりわからない。 「落ち着け!まず落ち着け!」 こういう時こそこちらが冷静でいなくては。もはや義務感に似た思いで、彼はとっさに手元のカップに紅茶を勢いよく注ぎいれ、いまだ意味の分からないことを喚いているアルフレッドに手渡す。一気にそれをグイと飲み干したアルフレッドが、ようやく一息ついたようにほうっと持ち上がっていた肩を下ろした。寝起きなのだろうか、いつにもなして寝癖が激しく、眼鏡なんてほとんど鼻の先にひっかけただけの状態だった。 「ちょっとは落ち着いたか?」 アーサーの質問に、アルフレッドがこくこくと何度も首を縦に振る。 「で、どうしたんだよ、がなんだって?」 「そうだよ!!」 その言葉にまた、アルフレッドが激しい身振り手振りで慌てだす。 「アーサー!君なにか知らないかい!!昨日オルカと飯食ったんだろ!?」 その勢いに圧倒されながら、それでも質問の意味がわからないアーサーは、再び黙って紅茶を差し出す。それを素直にもう一度受け取り、豪快に一口で飲み干して、アルフレッドはようやくずれたままの眼鏡に気が付いたらしく指のさきでフレームを押し上げた。 「今までこんなことは一度だって…!!確かに僕はの友人だけどそれ以前に仕事なんだよ!!もしもになにかあったら…!ああっ!そんなことがあったら!!!」 「アル、アルフィー、だからちょっと落ち着けって、な!な!?がどうしたってんだよ?」 懐かしいあだ名にハッとしたのか、一度咳払いをしてからアルフレッドが居住まいを正す。 「今朝起きたらこんな留守電が入ってたんだ…。」 途方に暮れたような声音で、アルフレッドが携帯電話を取り出した。ちょっと失礼して耳に当てると、機械が昨晩の内に録音されたメッセージを繰り返す。 『…も、もしもし、アルフレッドさん…?です…うっ、』 泣いている、というわけではないようだが、憔悴しきった声だ。こんなにも弱ったの声を聞いたことがないアーサーも、思わず緊張に身を固くするような話し方。ひょっとして突然刺されて死にかけた人間ってこんな声を出すんじゃないだろうかと想像してしまってぞっとする。 『ちょっともう―――ムリ、耐えられそうにありませ…だってあんな、×××××?××××××!×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××―――×××!×、×××××××××××××ピピッ。』 一体なにがあったというのだろう。しかしながら最後が全く何をいっているか、アーサーにはちっともわからなかった。それが言語であることさえ、若干疑いたくなるような。なんとなく、ビデオを巻き戻しているような音だった。しかも途中で、途切れているような雰囲気だ。 どういうことだと無言で見上げるアーサーに、アルフレッドもまた、憔悴した様子で眉を下げる。 「僕もの星の言語を完全にマスターしてるわけじゃないからわからないけど―――なんであんなものが存在しているのかわからない、おそろしい、しびれる、浄化されるまで戻らない、旅、いややっぱもう無理、死ぬ、はわかった。」 何回かけなおしても電話には出ず、自宅に至急お抱えのエージェントを向かわせたが見当たらないと言う。 一体どういうことなのだろう。 ただどう考えても、これを聞いてアルフレッドが取り乱したように、の身になにかおぞましい、おそろしい自身信じられないようなことが起こり、どうやら無事らしいが彼女が自ら姿を消した―――らしい、ということは明白だった。米国によって手厚く保護されているはずの異星人になにかあったとなれば、アルフレッドもただでは済まないだろう。どうしようどうしようと庭をうろうろ歩き回るアルフレッドに、アーサーはかける言葉もない。それにに、いったいなにが起きたというのだろう。 昨日会ったときは、普段となにも変わらなかった―――と思う。いつも通りの無表情、いつも通りの化粧っ気のない顔、いつも通りの冗談かわからないジョークに、やっぱり笑うとかわいらしい顔。いつも通りだ。じゃあまた、とお互いいつものように手を振った。そのいつもの延長線上に―――二人がお互いの家の方向へ歩き出したその後に、いったいどんな恐ろしいことが起こったのか。 家まで送っていけばよかった。 携帯電話を握りしめたまま呆然とするーサーの片目から、思わず涙が飛び出そうだ。 家まで送っていけばよかった。せめて曲がり角をまがりきるまで見送るとか、帰ってから無事家に着いたか確認の電話をかけるとか―――。 次々と湧いてくる自責の念に、アーサーは立っていられなくなった。 思わず座り込んだ椅子の横に、アルフレッドが立って本当に困ったときの顔でアーサーを見下ろした。 「アーサー、君、に最後にあったのは多分君なんだ。どんな些細なことでも構わない…なにか変ったこと、なかったのかい?」 少し冷静さを取り戻したアルフレッドの瞳は、落ち着いた青味を取り戻しつつある。くたびれたように前髪が、まつ毛の上に落ちかかっている。それを眺めながら、アーサーはついには立場が逆転しつつあるのを自覚した。今となってはアーサーの方が、ガタガタ震えて落ち着いてなどいられない。 「きの、昨日はなにもなかったんだ―――いつも通り、いつも通りだった。」 一言一句逃すまいと、アルフレッドはアーサーの言葉に耳を傾けている。 「土曜日は暇だったし、が取材で仕事場の近くに行くっていうんで、案内するって言ったんだ―――案内して、そこで一旦分かれた。本屋とコーヒーショップで時間をつぶしてるうちに取材はすぐ済んで、それで昼飯を食いにいった…中華食った…ええとそれで、原稿を仕上げねぇといけないからって言うんで、そのままメトロで帰ったさ…いつもの門で分かれて、じゃあまたな、って言ったらもいつも通りまたって言ったんだ…。」 また、と言ったの顔が思い出された。 「なにかその時変わったことはなかったか?なにか―――なにか、いつもと違うことをしたとか、の様子がおかしかったとか。」 いつも通りだったはずだ。の様子にも特に変わったことはなかったし、アーサーもそうだと思う。周囲のことにそこまで気を配ってはいないが、危ない目にも合わなかったし、つけられていた、とかそういうことはない、と思う。 手がかりらしい手がかりもなく、しかしアーサー以外に手がかりのないアルフレッドは、今度こそ完全にアーサーの知らない常の冷静さを取り戻したようだった。眼鏡の奥で青い目が、真剣に冴え冴えと光る。 「OK.アーサー、もう一度、最初から、昨日オルカに会ったところから…細かいところ、会話、食べたもの―――思い出せることは全部洗いざらい上げてみてくれ。」 その言葉になんとなく取り調べめいたものを感じながらも、友人のピンチだ、アーサーはゆっくりと頷くと、もう一度昨日の出来事について回想し始めた。 ―――集合は10時時だった。彼が待ち合わせの場所に時間ギリギリに着いた時には、やはりはもうついていた。それで取材に行っていいのかと思わず聞きたくなるような、いつもの通りのラフでシンプルな服装をしていた。いつもの。そう、白いシャツに細身のジーンズ…いや、確か一応は取材だからと言ってジーンズじゃなく綿のパンツだったかな。まあとにかく、そこまでいつもと変わらない服装をしてた。そこから10分ほど歩いて、の取材先に着いた。取材先と言っても、まだその段階じゃなく (取材先は金融街の古くてアンティークな、少しデザインのこじゃれたビルだ。建築がおもしろいって言うんで、最近じゃ見学ツアーも組まれたりしてるらしいが、至って真面な金融会社だ。) そのビルの一階のロビーで広報担当者と取材の日程の打ち合わせをするってことだった。30分くらいだろうと聞いてたがその通りで、本屋で本を三冊ほど見繕って、コーヒーを急いで飲んでちょうどくらいだった。コーヒーショップまでが歩いて迎えにきて、そのまま昼飯を食おうと言う話になって―――でも特に思いつかなかったから、中華料理やのテイクアウトをそのまま店先で食った。食べながらこの後の予定の話になって、が原稿を書かないといけないのですみません、って言って仕事だろ、って俺も言って、それで食べ終わったらさっさと解散、てことになった。寄り道しないで歩いて―――歩いてる途中も特に変わったことはなかったな、メトロに乗って、駅で降りて、そのままいつものルートだ、お前も知ってるだろ―――を歩いて帰って、分かれ道で別れた。本当にいつも通りだったよ。」 お手上げだ、というようにアーサーが頭を抱え、しかし顎に手を当ててそれを聞いていたアルフレッドが、首を傾げる。 「…アーサー、君、なんで集合時間ぎりぎりになったんだい?」 米国生まれの自称英国紳士は、遅刻というものをしたことがほとんどない。集合時間の30分前には、予定が楽しみ過ぎて到着してしまうぼっち男だということくらい、幼馴染はよぉく知っている。 「えっ、」 予想だにしなかったのか、その質問にアーサーは顔を勢いよくあげた。 「えっ、って君…まさか…。」 「違う違う違う!なにを想像してるのかわからねぇけど絶対違う!!」 「…じゃあなんなのさ。」 「そ、それはだな…、」 アーサーが口をとがらせてなぜだかもじもじし始めた。正直大分、この緊急事態にこの態度は、うっとおしい上に気持ちが悪い。さてアルフレッド・F・ジョーンズの特徴のうちのひとつとして、良くも悪くも素直であるということがあげられる。 「うわあ、君、うっとおしい上に気持ち悪いよ。」 こっちは緊急事態なんだからさっさといいなよ、と素晴らしい切れ味である。アーサーは言葉のナイフにぐっさり刺されながら、それでもの緊急事態と言う単語に怒りとやるせなさを抑えつつ、小さな声で言葉を発した。 「―――――をだな、」 「なんだって?」 最初の方が聞こえなかった。 「だから、スコーンを、だな。」 その言葉に、アルフレッドがみるみるうちに青褪める。 「早起きして焼いて持って行ってやろうと思ったんだが、作ってたらちょっと材料が足りなくてな?買いに行く時間はないし、家にあるものでどうにかしようとしてたらギリギリになっちまって…でもちゃんとできたんだぜ!残った分は今朝の食事にしたが今回はなかな―――か?」 最後まで言い終わらないうちに、ハリウッドのスタントマンもびっくりの身のこなしで、携帯電話を耳に当てながらアルフレッドがこわした垣根を飛び越えて去っていった。大至急救護班もの自宅へ!とか重度の刺激物を摂取した可能性、とか叫んでいる。 「とにかく携帯の発信記録を元に自宅周辺の徹底的な捜索を!作業員もっと増やして!幾ら■■■星人がタフとはいえ、あれを初めて食べてそんなに歩けるはずがない!!」 遠ざかってゆく幼馴染のなんだか頼もしい背中を見ながら、しょもん、とした顔をした自称英国紳士がひとり。 |
(20120112)