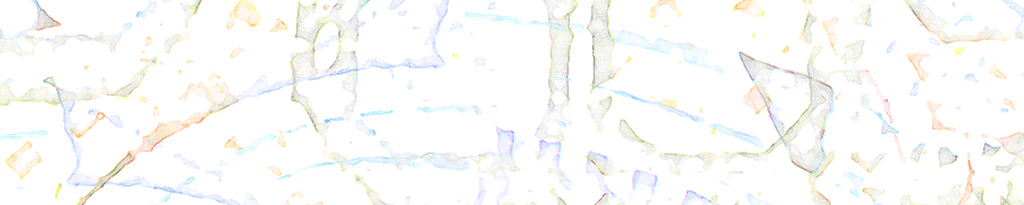
あぢさゐ歌
しとしとと途切れることなく霧のような雨が降り続いている。軒に積もった水滴は、ゆっくりと膨らんでは、ぽっしゃり、とん。
雨の音にも拍がある。
気づくとひっそりと、なんだか楽しい心地になった。ぽったん、ぴん、ぽっしゃり、とん。太鼓に鼓、とんたんとん。
それを聞いている間に、少しうとうとしたようだ。
敦盛がはっと顔を上げると、雨の庭は紫陽花の盛り。はちきれそうにまん丸な、青い鞠が、塗れた緑のなか、いくつもいくつも転がっている。少し夢のような景色だった。まぁるい花は、真っ青で、先だけ淡い紅色だ。両手に童子が抱えたら、きっと本当に、見事な細工の鞠と見紛うだろう。
ぷっくりと膨らんだ花を、目覚めたばかりの心地で眺め、敦盛は少しぼんやりとする。雨は未だ止む気配を見せず、ただしとしとと、降り続くばかりである。食べたらきっと甘かろう。ふいにそんな風に、子供らしい言葉が浮かんで、彼は微苦笑を口元にのせると首を振った。
そんな年ではあるまいし。
本来ならば、歌でもひとつ、詠むべきだ。しかしどうにも、楽とは違って、彼には歌は難しい。美しいものに、ほろほろとこぼれてくる思いは、形にしようと手で掬うと、端からまたこぼれ落ちてしまう。桜の春を、錦の秋を、三十一文字に閉じ込める作業が、彼にはずいぶん魔法がかって難しい。どうして言葉にできるだろう。
そうして散々悩んだ挙句、いつも言葉に詰まって、彼は結局笛を吹く。
彼のこころからこぼれる思いは、吐息に混じって音になる。敦盛にとっては、言葉にするよりも簡単で、唯一、その心の内を表せるように思えた作業。
紫陽花の庭を眺めながら、それでも彼は数刻の間頭を捻っていた。
五月雨の、春雨に、降り染めし、時雨降る、春の雨、なみだあめ、さみだるる、あぢさゐの―――。
思いつく限り、言葉を並べてみるがどうもしっくり来ない。
そこでもう一度紫陽花のあふれる庭を眺めやっては首を捻ってみる。ぽったんとんとは雨の音。
紫陽花の花の色こそ空の青に似ている、雨とも、涙ともつかない、優しい色だ。なぜこの花は丸く円を成すのだろう。優しいまろい輪郭。やはり食べれば甘いだろうと、彼は思った。
こういったことすべて、いったいどうして三十一文字に収まろうか。収めるためには削らねばならぬ、削るためには捨てねばならぬ。せっかくの美しい景色、捨てるも削るもあまりに惜しい。
「敦盛さん?」
ふいに目の前に白い紫陽花が咲いたと思った。
違う、これは声だ。思い直して顔を上げると、が背中に立っていた。
「殿、」
「ぼうっとしてましたね、考え事ですか?」
気配に気がつかなかったとは武人として恥ずかしい。歌を考えていた、とは言えず(言えば詠んでくれと言われるに決まっている)、彼はただ「少し」とだけ答えた。
ぽったんとん。雨はいい。
そうふいに思う。
彼はあまり喋り上手ではないから、しばしば生まれる沈黙を、雨音は優しく埋めてくれる。とん、たん、ぽっしゃり、とん。さらららら。雨の音。
隣に座ってもいいかとに尋ねられ、彼はことりと頷いた。断る理由はひとつもなく、ただ、雨音に紛れて聞こえないだろうが、心の臓がうるさい。紫紺の髪の間から、そっと覗き見ると、は紫陽花の群れに目を輝かせている。
「わあ、」
口元が笑みの形をつくる。神子といいといい、彼女たちの表情は明るく、あけすけで、彼にはとても、素直でつくしいものに見える。
「すごい!」
とふいにが、敦盛の方を向いたので、彼はビクリと肩を震わす。
なにぶん彼女の内に宿る、光は大きく、強すぎる。まっすぐな視線をなんとか受け止めながら、内心彼はどきまぎと、また心臓が動き出すのを感じる。もう生きていない身であるのに。一度死んだ心臓、一度滅びた肉体。なのにまだ、こうして胸が鳴るのはなぜだろう。なぜだろう。
考え出せばいつだって、せつなくてせつなくて、よくわからない。ただせつなくて―――悲しいのに嬉しいのだ、間違いだと知っていても、生を本能が望んでいる。もはや生とは程遠いところに来てしまったにも関わらず。
「紫陽花、すごいねぇ!」
「あ、」
「ちがった、すごいですねぇ!」
本当に輝きだしそうな笑顔だった。彼は思わず、言葉を止めた。
それをも気にせず、はすごいすごいとはしゃいでいる。
"すごいねぇ!"
笑顔。心の臓がうるさい。ああどうしてこんな柔らかな優しい雨なのだ、この音が聞こえてしまうではないか。
雨は降り続いている。蚕の糸より細い雨だ。それが幾重にも重なって、塀の向こうはぼやけて見える。
「紫陽花がこんなにいっぱい!初めて見ました!」
が敦盛に、そう笑いかける。やはり彼は少し気圧されながらも、「…昔この寺に清盛叔父上が特別にと紫陽花を集めて植えられたのだ」とぽつりと答えた。
―――どうだ敦盛、見事だろう。
豪快な笑い声が、今もなお鮮やかに蘇る。
「そうなんだ…清盛って、なんだかんだ粋な人だったんですねぇ。」
感心したようにが言って、それに彼も「ああ」と返す。
「美しいもの、風雅なものには労も金も惜しまぬ方だった…その癖野の花を見てこの風情にはかなわぬなぁ、などと豪気に笑われたりもする。…面白い方だった。」
ふぅん、とが、なんだか優しそうな、嬉しそうな具合に目を細めて敦盛を見つめる。抱えた膝の上に頭をのせて、ことりと顔だけこちらに向けて。髪の毛がさらさらと、地面の方に垂れていた。
あんまり優しそうな瞳なので、敦盛はドキリと息を詰めさせる。時折この女人は、普段の明るさからは思いも寄らない顔を見せるものだから、心臓に悪い。
「みっ、殿は、なぜこちらに?」
あわてて話を余所に振る。わざとらしかったろうか。
チラと横目で伺うと、は特に気にした様子もなく「紫陽花が盛りだと聞きまして。」と答えた。
「そうか。京で紫陽花を見るなら、確かにここ以上の場所はない。」
「はい、とってもきれい!私ね、紫陽花好きなんです。まんまるで、かわいくって、青くて…なんだかおいしそうじゃありません?」
ふふふと悪戯っぽく笑われて、敦盛は思わず、「…確かにあまそうだものな」と言ってしまった。しまったと思った時には、彼が予想した反応とは逆に、はおかしそうに笑みを浮かべていた。
「ですよね!お砂糖菓子みたい!」
にこりと笑ってそれからが、「それに、」となお笑う。
「あつもりさんもいますしね。」
歌の詠みだしはこうだ、おもふひとの。
彼は固まってしまった思考のどこか遠くで考える。
あめ。ぽっしゃり、とん。
紫陽花の葉のしたで、蝸牛、少し笑った。
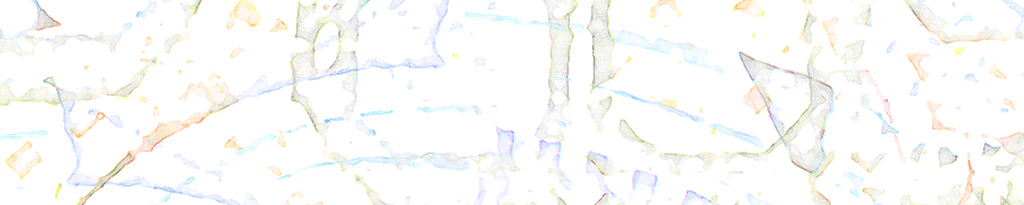
あぢさゐ歌