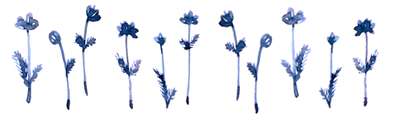「あなたってまるで子供みたいよ、スキピオ。」
そう楽しそうに笑った女に男は少し曖昧に笑みを返すだけだった。
実際子供に違いない。十分大人でありながら、彼は子供のままだったから。それを彼は幸運だと思ってる。運命の女神の祝福だと。
だからそれはもちろん男にとってほめ言葉でしかなかったはずなのだ。だけど、やはり、その本当に歳を重ねた女の言葉は、まだやわらかいままの男の心臓の辺りに渋く刺さった。
けれども昔から身についた彼の立ち振る舞いにそれは現れなくて、ただ彼は少し笑うだけだ。
「…子供だよ。」
ぼそりと小さく呟いた言葉は果たして届いたんだろうか?どちらにしても構わなかった。届いたところで理解れはしないだろう。きっとだれにも。
少年以外には。
彼にだって理解れはしまい。ただ判るだけだ。あの少年は選ばなかった。
いつだったか。かわいい人、と女は言った。ふっとほほ笑みながら細い肩を竦めて。Mio
caro、と言った。少年にはまだ難しい、美しい囁きだった。
伏せた瞼、薄いシガー、高い踵、彼女は大人だった。口角の形が美しかった。細すぎるような身体も。長い指先の人だった。薄い背中は骨が浮いて、少し硬そうにも見えた。
だが男は彼女が時折浮かべる少女のような表情が好きだったのだ。突然背後から声をかけたときや本気で心配をかけたときにだけ見れる、驚いて肩を竦め目を見開いた顔が。決まってその後くしゃりと顔を崩して笑い出す。その一連の動作が好きだった。それが愛なのか男はまだ知らない。まだ少年のままだったから。
細い首は男が指を添えて力を込めればきっとパキンと折れてしまうだろう。曖昧に笑って男は少し首の後ろを掻いた。
触れてはいけない、そんな気がしていた。まだ知らないからだ。覚えていることが多すぎて。女はまだ彼にとって憧れのままだったので。
なんとなくすっと目を合わせていることが躊躇われて、男は真っ白なプレートのふちを彩る花模様を、目で追っていた。白い滑らかな草原の、藍色の花々。
指でなぞるように、目でひとつひとつを追っていく。
それは皿の上の、幻の花々だ。
パスタはもうすっかり男の胃の中だ。
女はまだ食事を続けている。なぜだろうか、白いワインの透けるような黄緑が、男にはとても神聖な色に思われた。突然の感覚は一瞬で、男はすっかりそれを忘れて残ったワインを飲み干す。
女が顔を上げてあどけない微笑を浮かべた。
「おいしいね、スピキオ。」
子供にするように言い聞かせるような、優しい声音。ああ時が止まる。
男は目を見開いた。
その頬に触れたい。くちづけてみたい。こみ上げるようにそう思う。
どちらの動作も行ったことがある。ああ違うしかし違うのだ。
男は少し身を硬くした。
幻の花ですら摘んで見せよう。
テーブルを男の手がまたいで、女の頬に伸びる。しっとりとやわらかい。やはり現実だ。知っていたはず。
(これは同じ世界の生き物なのだ。)
憧れの終わりはシャボンが弾けるようにあっけなく、なんて魅惑的なのだろう。幻の花々、彼は摘むことができる。神であろうがなかろうが、男は摘むことができる、美しいいきもの。
「なに?どうしたの?」
低い声で微笑しながら、女が首を傾げる。ふっくらとした肌色のルージュ。大降りの耳飾。瞼のシャドウのスタータストブルー。
そのまま少し立ち上がって、男はゆっくり、女に顔を近づけていく。彼女は笑っている。ああ眩暈がする。なんて耽美な。
|