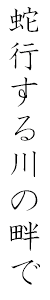 |
その川はうねうね蛇行しながらどこか遠くまで、黒々と流れてた。 灰色の街の真ん中を、我が物顔でただただ緩やかに。 街はもはや人間の暮らす土地としての機能を果たしていなかった。 かつて白かった建物は、暗く灰色に煙り、ツタが絡み、樹が生え、しかしそれすらも陰鬱な青い影を背負い。生命の気配が極端に薄く、ただ、暗い水色をしていた。 川は流れる。 何も私に関係はないのだと言って。 水面の黒は時折波立つと青くも見えた。黒白の街は仄青い。空は鈍い墨色。まるで失われた世界だ。 川の流れは、一見すれば止まっているかと思うほどに緩やかだ。河岸までの距離は長く、大河と呼んでも差し支えないのに、停滞している。大きすぎるから、そう見えるのかもしれない。動いているのに、動いていない。生きているのに、生きていない。死んでいるのに、その死すらないと。 灰色のボートを浮かべて、私は流れに浮かんでいる。 「死んだ水色の街の、」 読みかけの本の表紙は黒く、銀箔で文字が圧されている。意味は知らない。なにせ見知らぬ異国の、しかも古代の文字である。読めはしないが頁を捲るだけですべては事足りる。充足する。 「中心を横切る大きな黒い川の上で。」 私は節をつけて歌った。ボートを漕ぐだけの力は私にはないのだ。 「女は本を読んだ。」 流れに手を差し込むと、黒く見える水は透き通っていた。 岸辺の姫紫苑が、風もないのに手を振る。泥と灰に塗れた街にも、花は咲く。それは感動的なことではない。取り立てて論じるまでもない。通常な生命の運航。 「街は死んでいる。」 川の岸辺に男が立ってる。その背後に大きな象を連れていた。 街は静まり返っている。誰もいない街なのだ。川だけがここに人がいた時と変わらず、うねうね蛇行しながらどこか遠くまで、黒々とゆっくり流れてる。 「滾滾と湧きだすこの川の始流の様子を想像しようと女は試み、」 男はしばらく水面を見つめていたが、ふと顔を上げて少し口の端だけでわらった。 ボートの上で歌う私を見つけたのであろう。かすかにその目を見開いて、こちらを眺め、ほほえむ。 「この巨大な生命体の生まれた胎盤を想像できず、」 男がかすかに手を振った。 私も手を振り返す。ららららららららら。歌は続く。すべてはとりとめのない言葉遊び。意味などない。意味などない。意味などなくても人は充足する。満ち足りても満ち足りない、それすらも無意味なのだ。 「女はもう一度、ボートを浮かべる。」 象が小さく鼻を鳴らして、男は再びマフラーに首を埋める。 男の顔色は石膏のように白い。大きな黒い目と、黒い髪、真っ黒なコートと、黒いマフラー、黒い革靴。なんとこの町におあつらえ向きの男だろうか。 「やあ。」 「やあ、と男は言う。」 男は少し肩をすくめた。芝居じみたポオズ。 「とんだオフィーリアがいたものだ。」 「ボートには花に埋もれることも浸水することもなく、乾燥している。乾いている。男の言葉に女は首を傾げる。」 私はその言葉の通り、コトリと首を傾げた。 それにくつりと、男は少し笑った。 「オフィーリア、君の名を教えてくれ。」 「男は悪戯にそう懇願する。女は答える、ではあなたの名をわたくしにお与えになって。と。」 男はなおも笑った。彼の色は耳朶にぶら下がった青い石だけだ。 「クロロ=ルシルフル。」 「悪魔の名に似た響きを男は答える。女は名を答える。・。」 その青もまた、この街の色。象は暗い灰色をしている。 水面の縞模様を思う時、オールはいつも勝手に北へ進路をとる。 「、水遊びにはまだ寒いだろう。」 「男の問いかけに、女は立ち上がるとくるりと回って答える。」 ボートの上に立ち上がると、くるり、「女の白いワンピースの裾、」回り終わって男をまっすぐに見る。 「翻ってしかし何事もなかったように沈黙する。季節は夏でもあり、冬でもある。」 「寒くはないのか?」 「あなたは寒くはないのか?」 「寒くない。」 「では私も。」 男が何か言おうとするのを遮り、私はもう一度ボートの上で回った。 「男は驚き、ワンピースからむき出しの、女の白く細い方と腕を見る。」 男は無表情な目を丸くして、やはりかすかに笑った。 「ようこそ、ここは泥に塗れた水色の街。」 なお私は歌い、川の上から男へ優雅な礼を投げた。 「その川はうねうね蛇行しながらどこか遠くまで、黒々と流れてた。」 ボートはゆっくりと、男のいる岸辺から遠ざかる。 象が一度、高く鼻をあげて挨拶をする。 さようならと。 その川はうねうね蛇行しながらどこか遠くまで、黒々と流れていた。 この川は広く、深く、海へ続くかなどとんと知れない。沼地に似た暗い街を抜け、どこか夜の空へ続く。 私はやがて流れ着いた河岸に素足で降りると、またどこへともなく川に沿って歩きだした。振りかえった先にあの街は見当たらず、象のいななきももはや聞こえなかった。 |
| 20100902 |