「おや、…感心しないな。こんな真夜中に女の子一人が出歩くなんて。」 吸魂鬼がうろついているの、知らないのかな?それとも凶悪な脱獄囚が、うろついているのも、知らないのかな? 暗い廊下だ。背中から突然に声をかけられて、女の子は一度びくりと肩を震わせた。けれどそれだけで、その目は真夜中の外出を見とがめられたというのに妙に落ち着いて、どこかなにかを諦めきってもいた。 「ルーピン先生、」 こんばんは、と男の人が苦笑し、女の子は静かにこんばんはと返事をする。多分相手がおっかない寮監でも意地悪な管理人でも、彼女はそうしたろうと思わせる落ち着きがあった。寝間着の上にローブを羽織ったままの女の子は、裸足にスリッパを履いただけ。なんだかずいぶん寒そうで、なんだかずいぶん、心細げだ。 「…眠れないのかい。」 しばらく黙って、それから男の人が口を開いた。ずいぶん優しい、毛布のような響きだった。女の子はこくりと一度頷いた。それに男の人はふむ、と言って顎に手をやると、「ついてきなさい。」とそう言って歩き始めた。女の子は少し困ったように立ちすくんで、しかしその背中を静かに追いかけた。 てくてくという一定のリズムの後を、それより短くぱたぱたと小さな音が追いかける。 いつだったかしら、もう少しばかり、足音の数は多かったけれど、こんな夜があったな、と男の人は少しばかり懐かしい気がして、それから首を振ると角を曲がった。どうにもこのお城には、思い出ばかりが多すぎる。 角を曲がって、寝静まった階段を降りると、古い木の扉を開ける。 入っておいで、と笑って振り返ると、女の子は静かな猫のようにドアの隙間から入ってきた。そのまますすめられるまま、ストンと椅子に腰を下ろす。すると男の人は、どこか奥へ引っ込んでしまった。窓の外に三日月が見える。 静かな夜だ。 やがてコトリと目の前に置かれたマグカップを、女の子は少しぼんやりとしながら眺めていた。 「ココアはお嫌いかな。」 おどけたように片方眉を上げて発せられた言葉に、女の子は首を二回横に振る。 カップを手に取ると、じんわりとあたたかい。二人は同じように一口飲んで、それからやっと、女の子が口を開いた。先生、私ね。 「うん?」 「私…私、いつも夢見ていました。」 「なにをだい。」 尋ねる声音は優しいから、尋ねる声音はやわらかいから、ついつい勘違い、してしまうのだ。こわいものなどなにもないような、おそろしいことなどひとつもないような。まるでいつまでも起きていられるような。いつまでも死なずに生きていられるような、そんな錯覚をしています。 「いつまでも生きていられるんじゃないかって。」 ああ、とその人は笑って、それから静かに続きを促した。 「違うんです、なんて言ったらいいんでしょう。いつか死ぬってこと、知ってるはずなのに、自分には関係のないことみたいに、思ってました。」 そうだね、と相槌を打つ音は優しい。優しいからこそどの星よりも、多分女の子からは遠い。 「先生、私わかっているつもりです。世界は私が思うよりずっと、あっけなくて単純で、だからこそ情も何もなく、ただあるようにあると言うこと。それがどんなに私にとって苦しいことでも悲しいことでも嬉しいことでも、関係ないということ。」 むずかしいこと、かんがえるんだねと、馬鹿にした様子も感心した様子も含ませずに男の人はそう言った。どこか憐れむ響きがあった。 「先生私ね、気が付いたんです。例えば夏休み、最後の日に、パパとママがソファに座ってテレビを見ています。その背中から近づいて、私はオブリビエイト、って呟くだけでいいんです。それからロンドンの駅に着いて、同じコンパートネントに乗る友達が、さあついたわよ、って列車を降りるその背中に、同じことを呟くんです。そうして私のこと、知っているすべての人にその呪文を贈りおえたら、私、世界のどこにもいないものになるんです。」 そうだね、とゆっくりその人は頷いた。 テク、テク、テクと時計の音だ。静かな夜で、でもきっと彼らと同じように、どこかで誰かが目覚めているだろう。 「…そうするつもりだったの。」 どこか確信めいた問いかけで、もうすっかり冷めかけたココアを見下ろして、女の子は力なく頷いた。 「できなかったんだね。」 「ええ、できなかった。」 ぽたんとココアに、海の滴がひとつぶ。力なく椅子に腰かける女の子は、男の人から見てかわいそうな壊れたお人形のように見えた。それはもちろん頼りない蝋燭の光がそう見せるからで、今目の前にいるのが生きた人間の女の子だってこと、彼はわかっていたので、その不安にだいじょうぶさと自分で音のない声で語りかけた。 だいじょうぶさ、だって世界はあっけなくって単純で、だからこそ情も何もなく、ただあるようにあるんだろ。だから残酷にだって優しくだって、どっちにだってなんにだってなれるんだろ。夜が暗くて道が分からない。どっちが前だかわからない真夜中は、自分でどっちが前だか決めてしまえばいいんだ。むずかしいけど。てく、てく。脚が進む方がきっと前だよ。そう思う。 「先生、私、―――治るかしら。」 もう少し、もう少しだけ。大人になって誰かと出会って、行きたいところに行って見たいものを見て、それから、それから。少し月が影って、なぁにもともと頼りない三日月の明かりだ。蝋燭の灯りが、ちょうどフランドルの絵画みたいな具合に女の子を右から照らした。そうして時計の音はてく、てく、だ。そう決まってる。 「…なんて言って欲しい?」 女の子はちょっと口端を持ち上げてそれから黙った。海が溶けてもココアは甘いまま、ただおやすみなさいはいつも優しい。時計の音は心臓のリズムに似ているね。夜も更けたよ、ひとりごとはそろそろお終いにして、だいじょうぶ、あと四時間もすれば朝が来る。 おやすみなさい。 |
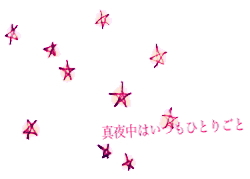 |
| 20130116 |