|
月も霞んだ二月の夜は、早くお家へ帰ろうと、急ぐ足先はやります。おぼろに寂しいあなたの夜は、うらうら揺れる雲の海、眺めて眠る宵の夢、閉じた目蓋も凍えます。 いつかの夢の話です。 幕を隔てた半月の、向こうを覗いたことがある。河のほとりで真っ青な、花を摘んだの覚えてる。ただそれだけの、それだけのこと。生まれる前と、死んだあと、そのどちらでもない、おぼろな夢の、遥かな影を覚えている。 今は煙る霞の夜。空いっぱいの群青色に、月の光が混じります。こんな寂しい青色をした、少し肌寒い春の夜は、おういと誰かに呼びかけたくなる。おうい、おうい。あの月を見たか。半分に欠けて空から転けて、それでも笑っていやがるあの月さ。こんな静けさむなしい夜は、とげとげ悲しい牙を持つ、男も多分、嘆きます。 つまり平たく言うならば、男というのは僕のこと。 ああもう随分長い間、僕は悲しみ、苦しみに耐えた。しかしそれすらただの出来損ないの喜劇であるのだから困ってしまう。その悲しみは、もう随分とくたびれ果てて、滑稽なくらいだったから。まったくほんとに滑稽で、客がいたなら失笑だか苦笑だかの嵐。それこそ笑える悲劇でないのなら、笑えぬ喜劇だ。 馬鹿馬鹿しい、とつぶやく呪文で消えるのは妖怪だけで、あとには何にも残らない。 おうい。あの月を見たか。半分欠けて、笑っていやがる。 襟をたてて顔をうずめ、とぼりとぼり歩きながら、僕は月について考えます。 大昔はね、月はもっと地上近くにあったのだって。 本で読んだばかりの恐ろしい事実に、僕は身震いする。今でも十分近すぎるっていうのに、なんてこと。もっとあれが大きく空に浮かんでただなんて、想像するだに恐ろしい。しかしけれども、昔ずっと近くにあったなら、つまり今ではどんどん離れてるんだ。三億年くらい後には、すっかり遠く見えなくなってりゃあいいのにと思う。 三億年後のことなんて、君には関係ないのにって? いいや、それは間違いだ。例えば三億年前に、恐竜の僕がいたのなら、三億年後にも例えば空飛ぶ魚の僕が、いたってかまわないだろう。 三億年もの昔から、ずいぶん僕を苦しめた、あれが三億年後になくなるなら、それはどんなに、ことほぐべきことかしら。だからやっぱりそれでも僕は三億年後の僕のために、それを願わずにはいられない。 三億年のとしつきの彼方に、この願いが届かなくたって、せめて千と三百年後の野良猫の僕が、満月に今よりは苦しまないように。 そうしたらほら、僕の寝床のゴミ捨て場の向かいのきれいな教会に住んでる銀の首輪つけた君の、お月様みたいな金色の目、覗き込んで三億年前と少しも変わらないねと三角の耳元で囁くこともできるだろうから。 |
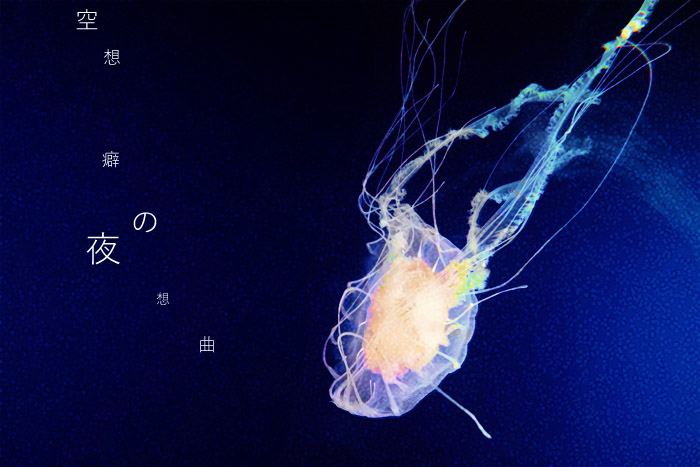
20150407