| よかった、よかったぁと全員が嬉しそうに手を叩きあって笑顔を浮かべているので、とてもよくないなどと言えなかった。「お前は隠し事できねーなィ。」
そう普段から呆れるように優しく笑われる彼だけれど、今日ばかりは、いつもの大味なくせに気の回る彼も、浮かれてそれに気づかないようだ。それとも忍ぶ恋のおかげで、ポーカーフェイスってやるができるようになったのかしらん。みんなと同じように、「良かったッス!」
と笑いながら、一度自分の頬をつねってみる。 「…いひゃい、」 どうやらわかってはいたけれど、やっぱり夢じゃないらしかった。 「なぁにやってんだィ、赤也!」 「ふふ、夢ではないぞ。」 だってぇと声を上げた彼に、どっと明るい笑い声が上がった。夢じゃない。よかった、よかった、とみんなが言う。そうだ、ほんとうに、よかった。けれどもこのこころのおきばが、彼にはどうにも見つからない。迷子のような目を、知らずしていただろうか。 ふとたくさんの人越しに目が合ったその人は、困ったように、ふにゃりと情けない笑い方、してみせたのだ。 |
◆ ◆ ◆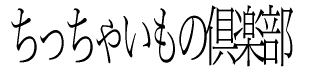 ◆ ◆ ◆ |
ポカンとしている。ぽかんとしていた。 てくてくと並んで歩きながら、赤也は空を見上げた。 何とはなしに胃の上あたりを覆うように鞄を持っていない方の手で押さえる。左胸を抑えるには、そこはジクジクと赤く傷んでいる気がしたので。も黙っている。てくてくてくと、情けないような足音を聞きながら、赤也はなんだかまだ夢を見ているような気がしている。 ぽかんとしてらぁ。さっきからそればっかりだ。どちらもすっかり、こころの真ん中に突然抱える羽目になってしまったまぁるい穴を、未だに信じられないような気持で持て余しているのがお互い手に取るようにわかった。昨日まで、いや、つい3時間ほど前まで、そこにはぎゅうぎゅうに、うれしいもかなしいもせつないも詰まっていた。なのに今では、どうして穴が空いているんだろう、って不思議に思うほど、ぽっかりそこがトンネルになっている。手を通して握手ができそうな、小さくておおきな穴。空にはぽっかり、満月が光っていて、ひょっとして、あれ、穴じゃないかななんて思った。空いっぱいに広げた黒い画用紙を切り取ったまぁるい穴だ。その向こうから、昼間の光が漏れているんじゃないか。 その思いつきは随分と、真理をついているように思えた。あれは夜にあいた穴から、漏れ出る昼間の名残。そう考えたほうが、どんなにか夜は明るいことだろう。 もうすっかり日は落ちて、蝉の声がかすかに残っている。 瞬きをしたら、昼間の、肩を並べていかにもお似合い、寄り添って歩く二人の姿が浮かびそうで、思わず舌打ち…もできそうにない。だってそれほど、二人は完璧に見えたのだ。 失恋だ。 完膚なきまでにこてんぱんだった。文句のひとつも言えないくらい、涙もひとつもでないくらい、感情の起伏が激しく誰にだってわかりやすいと言われる赤也がそんなそぶり一つも見せないくらいに、成就した恋は完璧だったのだ。ぽかりと開けた口から、二酸化炭素だけ勝手に出ていった。見えないそれに目を凝らすように、それを透かして空を眺めていると、ようやくが、ぽつんと口を開いたのだった。 「…二人そろって失恋したねえ。」 その言葉にびっくりして、隣を見ると、は情けない顔でそれでもわらっている。口調はまるでおかしそうに言ったけれど、ちっともおかしくない。言った本人の顔も、笑っていたけどどちらかと言うと泣きそうだった。 赤也の好きだった女の子と、の好きだった男の子が、恋をして今日やっとお互いの気持ちを告げあってしあわせになった。やきもきと見守っていたテニス部のメンバーは、全員諸手を上げて喜んだ。みんな誰より、その男の子にはしあわせになってほしいと、そうなる権利があると考えていた。もちろんと、赤也だってそうだったのだ。二人とも、自分でも驚くくらいにうまく、抱えていた気持ちを背中に隠して、他のみんなとおんなじように、彼の言葉に女の子が頷くのを校舎の影だとか植え込みだとかに隠れて見守っていた。彼女がはずかしそうに、けれども満面の笑みで、うん、と言ったとき、みんな思わず立ち上がって歓声をあげて、おかげで死ぬほど恐ろしい目に合ったけれど嬉しくってだきあいながら笑っていた。そうして騒々しいお祭り騒ぎのような時間が終わった後で、気がついたら、最中に隠していた気持ちが胸に穴を空けて、そのままゴロンと冷たくなって転がっていたのだ。拾い上げても、もうなにも言わない。 さみしい、かなしい。 うれしい。 すき。 すきでした。 指先で転がすと、壊れた録音機みたいにそれだけ。 ごめんね、と抱きしめたらまだ内側がほんのりとあたたかくて、けれども好きな人がしあわせそうでうれしそうで、自分のためだけにそれを抱きしめて泣いたり悲しんだりなんて、できっこなかった。 「…赤也よ、泣いたってよいんだよ?」 両手を迎えるように広げて、ことさらにおどけた口調、がへらりと笑って見せる。ヘッ、と殊更生意気な感じを意識して、赤也は口を尖らせた。 「…先輩だって泣きたいくせに。」 しまったなと言ってから思ったけど遅かった。泣きたくなんてないッスよ、こんなのぜんぜん、へっちゃらッス。とでも言ってやればよかった。 けれども実際、こんなのぜんぜん、へっちゃらなわけないので黙った。黙っていたら、そうだねえ、とのんびりした、よく注意して耳を澄まさないと普段と同じに聞こえるの声が静かに答えた。 「でもほら、だって私は、先輩だからね。後輩が泣いてたら、慰めてあげなくちゃ。」 「…泣いてないッス。」 「おねーさんの胸でお泣き?」 一つしか違わないくせに!と赤也が叫んだら、やっぱりのんびりと、の声が、そうだねえ、と繰り返す。 「たった一つだけど、君より大人だからさ。」 そうだ、たった一つだけど、大人だったあの人は、たった一つだけど、大人だったあの人と、恋人になった。 そう考えたら、苦しくて喉の奥が引き攣った。空っぽだった穴に、ぱたりと水が落ちた。かなしい。けれど泣きたくない。泣きたくなんてなかった。あの人がしあわせでうれしい。あんなに苦労して、病気もして、たくさんのものを背負って、それでも重圧に負ける素振りなんてみ見せずに、堂々と立っていた、誰より強くてたくさんの苦難に襲われて苦労したあの人が、しあわせになってうれしい。優しくて、かわいくて、あったかくって、わらうとお花みたいな、誰より大好きなあの人が、しあわせでうれしい。お似合い、本当にお似合いなんだ。二人そろうとほんとうにやさしくって、見てるこっちがてれくさくってさ。噫どうかお願いだ。本当なんだ。嘘なんかじゃない。本当の気持ちなんだ。そう思わせてほしい。だからその人の気持ちが手に入らなくってかなしくて、そんな自分を憐れんで泣くなんてまっぴらだ。 なのにこんなのってない。 ぱたり、ぱたりと空洞に水が落ちる。 「…俺、はやく、大人に、なりたい、」 そうしたらあの人も、少しは自分のこと、男として見てくれたかな、なんて。 俯いて黒い髪で顔を隠したまま、赤也がつっかえつっかえそう言ったら、たった一つ年上だからっていう理由だけで泣かないでいるが、「うん。」 と穏やかな声で相槌を打った。髪の隙間から、滲んだ視界でそっと様子を伺ったら、いつも試合のベンチで、コートの選手たちを見守る時のようなまなざしを、はまっすぐに道の向こうに向けてた。肩までの長い髪が、夜の風に静かに揺れてる。 いつもその透き通るような眼差しを、は彼にだけ注いでいた。その目が今はただ、いつもと変わらないくらい帰り道の向こうを見ている。どうしてだろうか、赤也にはそれが、とてももったいないことに思えた。 あの人よりももっとずっと前から、この人は部長のこと、好きだったのに。 ずっとずっと、好きだったのに。 そう思ったらまた、顔を上げてはいられなくなった。ぱたり、ぱたり、水はひたひたに満ちて穴からこぼれて、地面にも落ちた。ただ溜まらずにアルファルトに沁みてく。 てくてくと隣を歩くあたたかい塊が、いてよかった。たしかにたった一つだけれど、は赤也より大人なんだろう。甘えている、と赤也は思った。甘ったれている。おんなじような穴を抱えてしまった、たった一つ年上ってだけの女の子に、俺は甘えている。みっともなくて、ダサくって、たまらないのに、あんまりやさしくって、いけないな。 はなんにも言わないけれど、たしかに慰められている。 「先輩も、泣け、ば、いいのに。」 ヒッとしゃくりあげながらそう言ったら、そうだねえ、とやっぱりのんびりは言うのだ。たった一つ年が上だからってだけで、が赤也の前で泣けないのなら、それって本当に、理不尽なことだと思う。と、いうよりも、たった一つ年下なだけだけれど、多分そのたった一回りのその分、自分が情けなくって頼りがないってことだろう。そこに思い当たって、赤也は思わずグッと涙を引っ込めてしまった。 なにそれダセエ。 手の甲で頬を拭うと、兎になるよとがわらった。 「俺が、もうチョイ大人だったら、先輩、泣けますかね。」 涙声のそれに、きょとりとしてがやっぱりわらった。あとちょっとで泣きだしそうなのに、絶対泣かないんだな、と赤也は思う。 「先輩、いつ泣くんスか。どこで泣くの。」 思ったことを訊いてしまうのは、赤也の美徳だな、といつだったか柳目の彼が言った。 赤也のそれは、本当に心配そうな声音で、は一度、堪えるようにキュと目を瞑って、それから苦笑した。 「…さあ、いつかな。」 「俺、…早く、大人になります。」 ひとまわりなんて、関係ないと笑い飛ばせるまでくらい。あは、と声をたててがわらった。ぐす、と鼻を鳴らしたのはどっちだったろう。 「じゃあ赤也が大人になるまで泣かずに待ってようかなあ。」 空には相変わらず、ぽっかり明るく穴が空いている。 |
(20120831) |