| こういうことって、たまにないか。昔、いつ見たかもわからない映画で見た景色に、ふいに迷い込んでいるような、そのワンシーンをそのまま再現しているような。変に空気がセピアがかって、光がまぶしく、風はぬるくやわらかくて、風景はみなスロウ。緩慢に進む時間の中、どこかでフィルムが回る音がする。一度見たシーンの直中にいる。あるいはかつて、こんな景色を見たことがある。そんな感覚おぼえること、たまにないか。 「前もこんなことあったっけ。」 ふいにそんな言葉が口をついて出て、慈郎は自分で首を傾げた。どうせ半分眠りかけていた頭の発した言葉だから、その本人にだって意味するところはわかりゃしない。けれどもなぜだか、ああ、昔もこんなことあったなと思った。 自分は眠りにつこうとしている、それをが、優しいような、悲しいような、静かな眼差しで、目を逸らさずに見守っている。そういう場面。 「前って?」 腕から顔を上げなくたって、のきょとりとしている顔が浮かんだ。ずいぶん幼い頃から見慣れているから、目を瞑っていたって声の調子で顔がわかる、っていうのはうぬぼれかしら。尋ねられて慈郎は困って、けれども寝ぼけた頭が勝手に答えを出した。 「…むかぁし。」 そう言った声の調子は、なぜかな、すこし自分のものではないようにも聞こえた。 「…ねえジロちゃん、」 たっぷり黙ってが声を出す。 滋郎はときどき、いつでもそうだ。の声を目を閉じて聴く度に、不思議に懐かしい気持ちになった。目を閉じていたってわかる。の背中に向かって、斜めに指す窓からの明かりと、白く黄ばんだカーテンの影が揺れている。その光と影のただなかで、彼女はきっと夢でも見たくなるほど美しい。白い神話の女神が着るようなドレスが風に靡いて―――って、ん? 少し顔を上げるまでもない、は慈郎と同じ学校の制服を着ている。夢の見過ぎだ。 「ん〜?」 「昔っていつ?」 涙で滲んだ声が尋ねた。 「ん〜〜?」 「ねえ、ジロちゃん、」 「んー…わかんない。」 「…忘れちゃった?」 「うん、あんまり昔のことでさ。」 「…―――昔っていつ。」 囁くような、涙声。 昔やっぱり聴いた声だ。この優しい声が、自分のためだけにこうして涙の色に滲むことが切なくって嬉しかった。その声がもう聞こえないところへいくことだけがかなしくってさ。噫、だから、泣くなよ。 ずっときみがすき。けれどもその時の自分には、好きというその愛の言葉が見つからなくて―――? いつだっけ? 不思議な感覚は、けれども眠たい頭にはとどまらずに逃げていってしまう。ペットボトルを振った時に現れては消えてしまう泡みたいだね。ゆらゆら、きらきら。パチンとも言わず消えるあのペットボトルの底に揺れる泡は、どこからきてどこへいくのかな。てつがくみたいだね。おかしいや。 「昔って…むかし、むかーし。」 「わかんないの?」 「わすれちゃったの。」 「…そっか。」 「そう。」 少しドキドキしながら顔を上げたら、がわらっていた。 いつもと同じ、慈郎のだいすきなほやほやした煙みたいなわらいかただったから、彼は思わず、ほっとして同じような笑みを返した。泣いてるかと思った。の目の中で、海は溢れてはいなかった。それがうれしいよ。くだらない話だけ、ずっと繰り返して、笑っていたいね。 ふふ、とやっぱり寝ぼけ眼のままもう一度笑って、慈郎はもう一度目蓋を閉じることにする。 すう、と眠りにつく一拍前の呼吸は、どうしてかな、死ぬ前のそれと似ている気がすると死んだことなんてないけれど、思う。 すう。 赤い目蓋の裏の暗闇は優しいね。生まれる前の景色にきっと一等近いのだろう。 「ねー、」 「なぁに、」 返事があること、当たり前に信じている。 「起きるまでそこにいてね。」 |
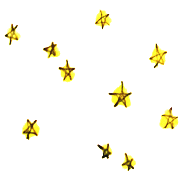 (玩具のような振る舞いで) |
(20121120)