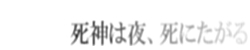例えば夢だとか希望だとか。
そんなもん鼻水かんでゴミ箱に丸めて投げ捨ててきました、とでも言うような女の子をひとり知っていた。知っていた。
今はもういない。
その子はとても大きな目をしていた。黒い目玉は白過ぎる肌の中でいっそう浮いて見えた。
少しこけた頬はいつだって冷たい。くちびるは乾いて荒れていた。痩せぎすの体は頼りがなくて、浜辺に漂着した白い枯れ木に似ている。細すぎる腕とその先にくっついた指は、それこそ本当に枝みたいだった。
きっときれいな女の子なのだということは誰の目にも明らかなのに、彼女は痩せ衰え、そして疲弊しきっていた。病んでいるのだ。それも随分と、長い間。
まだあんなに小さいのにかわいそうにねぇ、と誰かが言う。
その度に彼女が弱ってゆくのが目に見えるみたいだった。(そう、例えば、誰かが、)(テニスが強いって自慢なさってたのにかわいそうにねぇ、)(言う度俺から、コートが遠くなるのとおんなじ具合に。)
その子はいつも、挑むような、世界の何もかも睨みつけるような目をしてた。その大きな目玉をギラギラ光らせて、まるで目だけで生きているようだった。その表情はいつも強張っていて、変わることがない。笑ったら少しでも、顔に落ちる冷たいその影が和らいで見えるだろうに、どんなにか元のかわいらしい女の子に見えるだろうに、彼女はピクリとも笑わなかった。
出会いは衝撃的だった。
その子は松葉杖ついて、廊下に中庭からの光を背に立ってたのだった。左に重心を預けて、やはり俺を睨んでいた。季節は5月の緑が明るい昼間で、少し早い半袖の白いワンピースを着ていた。肩より長い髪の隙間から、その大きな目玉で彼女は俺を睨みつけて言う。
「あんたは治るわ。」
ものすごく不機嫌で、それでいてものすごくどうでも良さそうでもあった。
「…は?」
思わず聞き返してしまったのは、無理もないと思う。
「だから私が治るって言ったのよ。あんた治るの。よかったね。」
こんなにも投げやりで実感のこもらないおめでとうをもらうのは初めてで、ますますわけがわからずに俺は混乱した。
『とても珍しい…難しい病気です、』
医者の言葉がよぎった。それだけでこんなにも恐ろしいのに。
その子はじっと立っている。
「、ど して」
少し声がかすれた。
「どうしてそう思うんだい?」
その子は自分よりも幾分か年下に見えた。背も低く驚くくらい細かった。例えばここに、あの元気がとりえの同級生がいて、この子の隣ではしゃいだら、それだけで儚くなってしまいそうなほど。
つまらなさそうに、彼女はそっぽを向く。
「あんたの部屋では誰も死んでないもの。」
「は、」
「見つけたちゃん!」
看護士のお姉さんが、急ぎ足でやってくるのがわかった。しかしそれでも彼女は全く動じる様子はなく、この世のすべてを一蹴するような調子で言葉を続けただけだった。
「死人が出ると"げん"が悪いでしょ、だから死にそうな子しかそういう部屋には入れないの。」
「こら!ちゃん!」
どこでそんな根も葉もない噂話聞いてきたの、と僕を追い越して彼女に辿り着いた看護士さんがたしなめている。しかしやはり、彼女にはそんな大人の言葉なんて関係ないらしい。肩に手を添えてきた彼女を、真っ向から見上げて、その口を開く。
「だって知ってるもの。私ずっとここにいるのよ。由美ちゃんが研修に来る前からずっとよ。」
それにその若い看護士さんが、ぐ、と言葉に詰まる。生意気というには、あまりにも高潔な雰囲気が彼女にはある。
。改めて見つめ直したその子の細すぎる腕には、包帯がぐるぐる巻かれていて、点滴の針がまるでこの世の最初からの約束であるかのように刺さっていた。
(中略)
俺にはだんだんと分かってきていた。彼女がどうやって、子供たちにその世界の終焉を告げるのかを。
"治る"と彼女が断言する子供には、彼女は俺にしたように高圧的に、尊大すぎる態度で臨んだ。あんた治るわよ、と睨むように告げられたある子供は泣き出したし、ある子供は怒った。嘘付け!僕は病気なんだ!重たい重たい病気なんだぞ!治らないってお医者さんが言ったんだ!それにも、彼女はつまらなさそうにひどく馬鹿馬鹿しそうに笑うだけだ。
あら、じゃああんたの担当の先生誰よ?聖(ひじり)せんせ?訊いて来てあげようかあの子に治らないって言ったの?って。
そんなこと言うわけないじゃない、と心底うんざりした調子で言外にそう言っている。一回りも二回りも彼女より大きいその少年が、とても小さく見えた。
そう、彼女はそうやって、彼女曰くの"治る"人間にさっさとここから出て行けと告げて回るのだ。ここにお前は相応しくないここはお前のいる場所ではない。出て行け。と。ここは彼女の王国だった。白い壁に清潔すぎる匂いの充満した、薬品臭では隠しきれない、整理された死のにおいがする王国。彼女はそこの王女だったのだ。
その証拠に、は彼女の王国に"迎え入れる"側の人間が来たときにはひどく、普段の彼女を知っている者ならぞっとするほど美しく優しかった。
緑の溢れる中庭だった。俺は見てしまった。
やわらかい黄緑の中で、まだ6つかそれくらいの子供が遊んでいる。点滴をぶら下げた腕が、ひどく不似合いなほどぷくぷくと幸福そうな肌をしていた。さんさんと照る陽の中で、点滴を吊り下げた銀の棒の半径数メートル、その領域を、男の子は目をきらめかせて遊んでいる。何とはなしに、渡り廊下からそれを見ていた。病院にいてはたいてい暇で、そして部屋にこもってばかりでは気が滅入って、いけない。
草を踏む音にはっとして、顔を上げる。
気がつかなかった。がちょうど俺の死角から、庭に踏み出したところだったのだ。彼女もまた、いつもどおり松葉杖にもたれるように歩き、銀の棒をつれている。
「君、」
が言った。俺はびっくりしてまじまじと彼女を見た。その顔は、見たこともないほど穏やかで、優しく、しかしどこか恐ろしいほどなやましかった。なんて顔だろう。なんて、なんて邪悪で美しい、清らかな微笑なのだろう。日の光の下で青白く透けてしまいそうな肌をした彼女はとてもとても、美しかった。
「名前は?」
男の子はうれしそうに顔を上げて笑う。
「朔太郎!」
「…そう、朔太郎。」
「うん!」
「じゃあ朔だね。…ねえ、朔。」
の、細くやせた手が男の子の頭を撫でた。弟がいるなら、その子に対してするような、親しみのこもった動作。ゆったりと、優しく、慈しむように。それが合図だった。
なぜだかそれを見ただけで、知ってしまった、理解ってしまった。あの子は、あの子は――。
「早くお家帰りたい?」
「うん!」
「そう。帰れるといいね、早く。」
「うん!」
(中略)
「聖先生は、」
医者は顔を上げた。眼鏡をかけた、穏やかな微笑。短くて色素の薄い髪も、生来の優しそうな顔も、小児科医と聞くと誰もがぴったりだと思うに違いなかった。それでいてこののほほんとした雰囲気と裏腹に、この医者は病気も裸足で逃げ出しちゃうわよ、と言われるだけの腕を持っている。
「って子、知ってます?」
点滴の針を取り替えながら、彼がああ、と頷く。
「知っているよ。あの子は随分長くここにいるし、病室を抜け出す達人だしね…。担当でなくてもこの病棟の医者や看護士はみんな知っているんじゃないかな。」
よぉし、これで大丈夫。彼が笑って。少し俺の腕を優しく叩いた。ひどく親しみのこもった優しい動作だった。
「先生、俺、テニスがまたできるとおもいますか?」
白衣のポケットに手を入れて、立ち去ろうとしていた先生は立ち止まった。優しそうな眼差しが、眼鏡越しに向けられている。
「君はテニスがしたいかい?」
「…できなきゃ困ります。」
その答えに先生はきょとんとして、少し笑った。
「なら大丈夫。君がそう、望むなら。」
(中略)
「なんでわかるのかって?」
その目が暗がりで、ぎらぎらと光っている。正直に、恐ろしいと思った。この少女が自分と同い年であるということも、その目にだけ集中したような生命力も、すべて。
「部屋割りだけじゃ、ないんだろう?」
ニヤアとが、笑った。さも愉快そうに。
それと同時に、表情は消えた。ひどく怠惰で、さびしげな無表情だった。
「わかるのよ。」
「そんなのおかしい。」
「おかしくたって、わかるもの。」
その目が冷たく、光った。
「教えてくれるのよ。」
温度が急に、下がったように思った。
「誰がそん「おじいさんよ。」
「え?」
「おじいさん。どこから来たのか知らないわ。ずうっとこの病院にいるのよ。誰が死ぬのか死なないのか、どうしてなんでいつごろ死ぬのか。全部知ってるのよ。…この病院に来る子供のことは。」
あんたのことも、私のこともね。彼女が言う。
「……。」
「嘘だ、って思ってるんでしょ?私だって夢かと思ってたわ。でもいるのよ。」
彼女が何もないところを指差す。そこには暗闇があるだけだ。足元が抜けるような、怖気を感じて俺は後ずさる。
「おじいさんがね、わしの子、って言う子はね、みんな死ぬのよ。あんたは違った。あんたを指差しておじいさんは言ったのよ。おもしろい名前をしている、って。あんたは違うわ。」
君はなんと言われたんだ?それは訊けなかった。言葉すらでなかったのだ。その暗闇には、確かに何かが、いた―――。
「私はね、」
彼女が笑う。きっとその老人と同じしぐさで。ゆったりとその両手を、迎えるように広げて。
「よくぞ参った我が姫子(ひめご)、我が娘。首を長くして、待っておったぞ、そなたの生れ落ちたその時から。」
が微笑む。
「…まだ嘘だって思う?」
首を縦に振った。そうでもしないと、なにか、見えるような気がしたのだ。
「でも私だけじゃないのよ。」
耐え切れずにもう一歩後ずさった。ちょうど影になっての顔が見えなくなる。
「…父さんも小さい頃は見えたって。」
(中略)
昔々、病気の少年がおりました。
昔々、小さな王国の死を司る王がおりました。王には娘がおりました。
娘はたったひとつだけの命を持っていました。それは人間のように、増えたり減ったりすることはない、完全で、そして脆い命でした。
娘の仕事は、子供たちを王の玉座に導く歌を紡ぐことでしたが、ある日病気の少年に出会いました。少年には、王と娘が見えました。少年は、とても優しい気性の持ち主でありました。
王はその優しく聡明な少年をひどく気に入り、さまざまなことを教えます。病魔がどこに潜むのか。どこから病魔が忍び込み、いかに命を刈るものか。どこに潜めば見つかりにくく、またどんな部位に隠れるのを好むか。病魔が隠れ忍び、死を招く方法や、またそれらを祓うものたちのこと。少年はさまざまなことを学びました。病魔のことを知り尽くし、自らを蝕むものを恐れずともよいことを悟りました。…少年は治るのです。王が残念がることに。
いつか少年は娘に恋をし、娘もまた少年を愛しました。
ふたりは逃げ出しました。王の小さな国から。
少年は病気を退け大人になり、そして娘を妻に迎えました。
娘は子供を生みました。しかし娘の命は、たったひとつだけの完全でありながら不完全なもの――子供という器に吹き込む新しい命を作り出すことのできない彼女は、自分の命をまっさらに漂白して、子供の器に入れました。
こうしてその子供は生まれ、娘は永遠に命を失い、彼の手元にその子供だけが残されたのです。
(中略)
「あは、」
は笑った。
俺には何も、言えなかった。
「じゃあ私、もう毎日お薬たくさん飲まなくていいんだ、」
「…そうだよ」
医者の囁くような相槌は、ぞっとするほど穏やかで、ぞっとするほど優しかった。
「毎日毎日寝てなくていいし、」
「ああ」
「点滴1日3回も変えなくていいし、」
「もちろん」
「好きなもの食べられて、」
「好きな服着て、」
「行きたいところに行って、」
「駆け回って泥んこになったり、」
「精市にテニス教えてもらったり、」
「雨の中ではしゃいだり、」
「なんでもしていいのね?」
「そうだよ」
「なんでも。なんでもね?」
「…ああ。好きなように。好きなことをしていいんだ。」
初めて彼女は笑った。多分きっと心の底から。安堵にも似た、微笑。ぞっとしない。彼女の微笑はいつも、黒衣の聖母のような、あのぞっとするほほえみであったはずなのに。解脱したかのような、あまりに穏やかで、儚い笑みだ。そんなのは君じゃない。正直に恐ろしく悲しく、しかし心のどこかで安堵していた。死神はもういないのだ。
「好きなこと、できるのね」
「そうだよ、」
医者が微笑み、手をゆったりと迎えるように広げた。はフラフラと、熱に浮かされたようなおぼつかない足取りでその手の中に進む。
「父さん、って呼んでいいのね。」
「そうだね、。」
「ああ、おじいちゃんが言ってたわ、」
「ああ知っている。」
「この不良義息子って。」
「ああ。」
「私は良い子ですって。」
もうほとんど見えていない目玉でが微笑む。しごく幸福そうに。聖先生が初めてその穏やかな微笑を崩した。少し困った、泣き出しそうな微笑だった。
「…悪い子でよかった。」
(死神は夜、死にたがる/2008070220090224加筆)