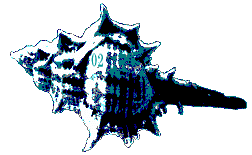 |
祖母の家は変わらず海沿いに、屋根を潮風に錆びさせて、少し傾くように立っていた。 祖母がいなくなってからも、近所の親戚が手入れだけはしてくれているようで、少しの間滞在するにはなにも問題ないようだ。 突然帰ると連絡したが、いつでも大丈夫だとたのもしい返事があった。思い立ったら吉日で、すぐに有給の申請を出した。季節はちょうど夏のはじめ、祖母の死んだ頃だった。亡くなったのはもう随分前で、高校に上がってすぐのことだったろうか。 雅治くんが帰ってきゆうならばあちゃんも喜ぶわぁ、と昔より少し老けた叔母の声が受話器の向こうでわらってた。なんにしてもいきなりのことじゃけん、一応かたしとくけど足りんもんがあったらゆうてねぇ。おっとりした声は父の家系だ。 田舎のバス停で降りる。 車の免許は持っているが、車を持っていない。レンタカーは置き場所に困るし、学生の頃のような気分で、彼は電車とバスとを乗り継いでここまできた。おかげですっかり、腰が痛い。 ぐるりと見渡して、懐かしいような、どこか古びた田舎道。見ればバス停まで、錆びていやがる。くすりとわらって、つま先で少し蹴ったら、こつんとかわいい音がした。 海沿いの小径を、幼い頃の記憶を頼りにあるく。古い垣根越しに、蜜柑の花が咲いている。 意外と覚えているもので、あっさりと迷うこともなく、懐かしい家が見つかった。少し傾いた家。見つけたら、なんとなくほっとして、荷物を土の上に落とした。 言われていた通り、さびた赤いポストを開ける。、茶封筒の中に、小さな鍵。 そういえば昔、その鍵を首からかけてたことをふいに思い出す。昔はこの鍵を、どんなに大きく魔法の鍵のように感じたろう。砂浜に扉を書いて、小さな鍵を回したりもしたのだ。 嘘の石を切り出してきて、自らの周りを固めるように、ぐるりと並べて置き出した。 それも確かこの頃だっけか。今や石は高く高く、賑やかしいお祭りの塔。てっぺんからは万国旗にシャボン玉。なあ、愉快なもんじゃろ。 「…ん、」 古い引き戸は昔と変わらず立て付けがわるい。少し格闘して、ああ、そういえば、思い出した。下の方を蹴りながら開けると滑りがよくなる。すんなりと開いた。こんなところまで変わらない。 ガラリと開けると、なんとなく暗い室内に、日の影がさしてぼんやり優しい光の加減になっている。斜めに差した光は、埃のにおいがする畳に落ちて転がっている。 「…変わらんのぉ。」 思わずひとりごとが、彼のくちから漏れた。 ばあちゃんがいないだけ。そんな気がする。もっと言えば、ばあちゃんの体が見当たらないだけだ。この家には、まだ彼女の気配が、濃密に残されている。ひょっとしたら、家と存在が同化してしまっているのかもしれない。霊感なんて、これっぽっちもない上に、幽霊なんてかけらも信じてはいないけれど。 狭い庭に面する縁側の障子を開け放つと、部屋の中は明るくなった。庭の木はずいぶん伸びたようで、縁側まで影を伸ばしてる。 よいしょと腰を下ろして、伸びをする。寝転がると日向のにおい。ああ、このまま猫になりたい。目を瞑ったら眠ってしまいそうだ。目蓋の裏はやわらかい赤色、なんとなく懐かしい色、している。 空が青いよ。海のにおい。ああそうか、会社でさぼった屋上に、足りないものは海の風、鴎も飛ばない。 やさしい日差しにうとうとしてきて、いけない、このまま眠っては夜になってしまうだろう。 無理矢理目蓋をこじ開けて、のそりと起き上がる。 さてどうしようか。 ぐるりと室内を見渡して、祖母の机の上に手紙が何枚か置かれているのを見つける。 一番上の、真っ白なはがき。ふいに鴎を思い出す。 ―――同窓会のお知らせ。 鴎じゃなくて鳩じゃったか。ひとりごとは塔の上。風に乗ってどこかへふわり。 白いはがきの日付は、半年ほど前のもの。ひっくり返して宛名を見ると、「…間が良すぎるじゃろ。」 。 |
>> |