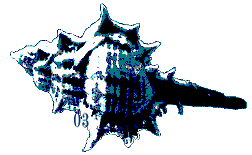 |
祖母の家の電話は、ひょっとしたらとも考えたけれど、やっぱりもう繋がらなかった。受話器を上げてもしんと静まり返っている。それが思ったよりも彼にはショックに感じられて、そっと受話器を下ろした。 ここに預けられたばかりの頃、迎えに来てとこっそり電話をかけた。母が出るだろうと思ったら誰も出なくて、がっかりした記憶がある。ここを出てからは、ばあちゃん元気かいの、と時々この電話に電話をかけた。 懐かしい黒電話。受話器を置いて少し表面をなぜる。 祖母が背中をまるくして、座って受話器を握ってた。骨と血管の浮かんだ手のひら。ばあちゃんただいま。雅治くんおかえり。そう言って通話口を抑えてわらって振り返る。 ああ、そう言えばただいまがまだだった。 おもむろに立ち上がり、仏壇の下を漁るが線香も蝋燭も見つからない。後で買いに行くか。それまで堪忍な、と彼は座布団に正座をすると手を合わせた。普段ちっともそんなことをしたり、しようと思ったりもしないので、誰が見ているというわけでもないのになんだか無性に照れくさい。 それから縁側に出て、携帯電話を取り出す。 ハガキの電話番号は自宅のものだろう。名字はで変わっていないし、住所から見てもこの辺り、おそらく実家で暮らしているということだろう。 時刻はうららかな昼下がり。本人がでるとは思えない。よいしょと、くつかけ石の上に足をおろした。角がとれてまろくなった平らな石は、陽の光を吸ってあたたかい。庭に下りるつっかけが、昔はちょこんと並べて置いてあったのだけれど、見当たらなかった。後でそれも探してみようかと、彼はのんびりと考えた。 いい天気だ。木がさわさわと揺れて、緑の影が乱反射する。 別に本人が出なくても、終わってしまった同窓会のこと、一言伝言を頼めばいい。もし日付に間に合っても、きっと行きはしなかっただろう。 通話ボタンを押す。一回、二回、三回…。コール音を聞く間になんとなく眠気に一瞬おそわれる。緑の光が梢の上で、水面のようにちらちら光る。どこか遠くで鳴るオルゴール、いつの記憶?石の塔の上で耳を澄ませる。 風に紛れて葉のこすれる音、潮騒に混じるオルゴール。足をぷらぷらメロディーに合わせて揺らせばいい気分。 『はい、です。』 オルゴール、いや、コール音が途切れて意識が引き戻される。若い女の声だった。 「あー…。もしもし、ええと、…さんおります?」 『どちら様ですか?』 「仁王雅治っちゅうもんですけど、同窓会のハガキをもろうちょったみた『におくん!』 懐かしい訛りが彼を呼ぶ。まったく1年ちょいしかいなかった、しかも小学生の同級生を、覚えて律儀に同窓会のハガキまで出すのだから変わり者だ。思わず笑うと受話器の向こうで彼女も笑う。 『久しぶりったいねぇ!ハガキの返事なかったけぇ、たぶん届かんかったんじゃろーなーとは思っとったんじゃけど!』 あーにおくんここにおったと!声だけならあのころとまったく変わらないように聞こえて、彼はますます笑いを耐えるのに苦労する。同窓会、行けばよかったなと、いまさら行けるはずもないうえになんだかんだで行く気もないのに少し思う。 まだ石を積み始めた頃だ、彼に花を差し出してきた女の子がいた。におくんと名前を呼んで、少しずつ高くなる石の塔に、梯子をかけて登ってきた。その花は、鉢植えに植えて、他の持ってあがったがらくたと一緒に、今も日当たりのいい塔のてっぺんに乗せてある。時々みずやりを忘れたりもしたけれど、しぶとく元気に咲いていて、今もてっぺん近くで風に揺られて、時々なつかしい歌、口ずさんでいる。 |
>> |