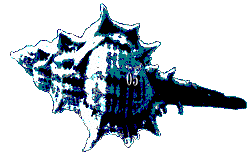 |
カツン、コン。ポトリ。カツン、カン。ポチャリ。 白い砂浜をしばらく歩いた。ぷらぷらと波打ち際を見つめて、ひょっとしたらテニスボール、漂着していたりはしないかと探したけれど、そう都合よくはやっぱりいかない。 ずるずるとラケットを引きずって歩いたので、砂上にはいっぽん、ふらふらの蛇みたいな線が彼の歩いた通りに残っている。これがコンクリートの上だったら、ラケットがひどいことになっただろう。なんとなく、砂をひっかくザラザラという音が楽しかったのだけど、中高大とテニスで一緒だった誰かさんにラケットをこんな扱いしているところ見られたら鉄拳が飛ぶだろうな。毎日顔を合わせないと、変なような落ち着かないような、奇妙な気分がしていたのは最初だけ。今では久しぶりに会うことが当たり前で、むしろよく毎日あんな濃いメンツと一緒にいられたもんだと誰にともなく嘯いてみたりして。 「よっ、」 さっきから彼は、適当にそこらにある手頃な石を拾っては、海に向かって打っている。間抜けな音と、間抜けな飛距離。間抜けが揃いも揃って、ちょっと笑えた。 カツン、コン。ポチャリ。 あまり続けると、本当にラケットがだめになるので、そろそろ止める。 空は思ったより白い色していたけれど、ずうっと遠くに明るく広がっている。朝っぱらからラケット片手に浜辺をぶらぶらしている若い男なんて、傍からみたらどう映るだろう。その想像も少しばかり間抜けで、やっぱり笑える。 砂の上に腰を下ろして、波が寄せてくる辺りを眺めた。 こうして眺めると、海が一つの大きな塊に見える。陸地を食む巨大な巨大ななにか。塔のてっぺんから眺める波打ち際は、ぞわぞわと白い波が蠢く世界だ。打ち上げられた砂と、浚われてゆく砂が、じゃらじゃら鳴って、波音に混じる。潮騒の響き。 それに包まれて、目を瞑ったら、あたりは海になった。ぷかりと彼の口から泡が浮かぶ。青い光が、揺れている。目のない魚が、泳いでゆく。白い色は彼と同じ。どこか似ているのかもしれない。 波にもつれて、さらわれてしまってもいいな。塔の上まで波は来ないが、海はやってきた。潮が満ちる。頬を気持ちがいい風が撫ぜてすぎる。塔の旗が風にはためく。洗濯物、干したらよく乾くだろうけど、きっと潮のかおりがつく。シャボンの匂いが好きだった。 波が思考を浚ってゆく。 耳の奥から泡といっしょに、メロディーが海に流れ出た。古いギターと、ヴァイオリン、それからオルガンに、ドラムスの、穏やかなワルツ。人魚の歌。 どこかで聞いたことがある。 でもね、それも嘘かもしれないよ。ポケットの中で子犬が囁く。石をあんまりきれいに積み過ぎたものだから、彼はときどき、嘘とほんとを忘れる。だってすべては嘘で、すべてほんとだ。表も裏も、白も黒も、彼にとってはどちらも同じになってしまった。だから彼の嘘は気づかれにくい。限りなくふたつのあわいに、きれいに立っているものだから。 詐欺師か弁護士になれる。 そんな風に予想された将来は、どちらも実現することはなく、いっぱしの会社員。サラリーマンというやつだ。 「怪盗にでもなればよかったのに。」 なんて言うどこかのだれかの夢見がちな驚きの声が思い出されて笑ってしまう。まったく後輩の勝利記念に久しぶりに全員がそろって食事をした時の話だ。幸村、このご時世に怪盗はないぜよ。そうかい?怪盗、いいと思うんだけど…怪盗…怪盗ちちんぷりぷり。ぶふっ、部長、止めてくださいよぅ! あれ、おかしいな。こんなところまできて、思い出すのは彼らのことだなんて。 目蓋を開けて、海から上がる。あたりは砂浜、もちろん海がまだ彼の周りを取り巻いている。波の形は鴎に似ているな。さっと横切った影は鳶だ。ああ、もうひとつ鳥の名前知っていた。 よいしょと立ち上がり、のろのろと歩き出す。 気分は軽く、今なら海の上歩いてわたって行けるように思った。砂は優しく彼の足をとる。もっとゆっくり、ねえ、もっとゆっくり歩いてよ。 ひかれるままに足を止めて砂を眺めると、おや、きれいな石。 なんとなく小さな頃、思い出してそのまま拾い上げる。よくよく目を凝らせば、あちら、こちらに小さな貝殻、角の取れたガラスの破片、ビールの王冠。 あの頃は宝物のように感じて、日が暮れるまで拾って集めたっけか。 漂着していたガラスの瓶に、拾ってひとつふたつと入れてみる。放り込む度にガラスが涼しい音を立てて鳴った。チリン。少し楽しくなって、ほとんどしゃがみながら浜辺を進む。この貯金箱じみた行為は、ではいったいなにを貯めているのだろう。 チリン。桜貝をひとつ。 何を貯めているか?答えは決まっている。海と夏とを貯めているのだ。いっぱいになったら一度家へ帰ろう。そう思いながらずんずん歩いた。空がだんだん、もっと明るく青くなって、透明に澄んできた。太陽が真昼に近づいている。砂が囁くとおり、ゆっくり彼は歩いた。メロディーはワルツ。嘘と空想はいつでも背中合わせ。とてもではないが、彼はまともではない。 ふいに砂浜の上の一軒屋に行き当たった。 これも夢かしらん。 丸太を組んで作られたらしい、素朴な風景。バルコニーの軒にいくつも真っ青なガラスの球がぶらさげられて、海と空の光を撒き散らしている。風が吹くたび光も揺れて、そこらに青い、夢を投げた。 塔の上の男は、そおっと小屋の正面に回りこむ。貝殻とガラスの看板。 『夏の家』 珈琲が500円。ランチもやって、いるらしい。太陽はもうほとんど、真上にある。そういえば朝食を食べていない。いつの間にかずいぶん時間が経ったようで、いつも朝食は食べないが、動き回ったのと早起きの分、余計に空腹を感じていた。 腕時計をちらりと眺めて、11時24分。看板には、オープンは11時半。あと6分。別段かまわないだろう。 もう一度看板を眺め、少し首をかしげてから、彼はバルコニーへ続く階段を登った。手の中でガラスが鳴って、それに答えるように軒のガラスたちがいっせいにさざめく。球の中には夏の光。瑠璃硝子の空。 |
>> |