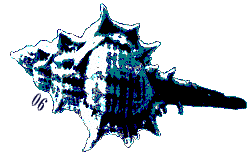 |
ウェルカムベルが金属ではなく硝子だった。張り詰めた高い音。海の結晶が砕けたらこんな音するだろうか。少し寂しい音のようにも、高潔すぎて冷たいようにも聴こえ、しかしやっぱり懐かしく、したわしい音のように思える。 ドアを閉めるときにもやはりベルは鳴り、ここは空の上、ここは海の庭――ふたつの言葉が転がった。真っ青なガラス玉、転がる。幾重にも重なったベルは、なんだか少しオルゴールに似ているかもしれない。 どこかで聞いた響き。 いつだっけ、同じように、窓の外に真っ青なガラス玉が、揺れて――― 「いらっしゃいませ、」 彼を現実へ引き戻す、店主の低い声もどこか懐かしいような響きを帯びている。 それにしても、映画でないなら絵本のような店だ。カウンターの向こうの店主の、白い髭と眼鏡の具合なぞ、熊のよう――おっと、夢のよう。その頭上で、まあるい時計が時を刻んでいる。11時半。ずいぶんながい散歩じゃったのぅ、と自分でも少し感心した。 にこりと目で促されて、窓辺の席に座る。窓の外には砂浜と、そこへ続く海が見えた。ゆったりと、ワルツ。現実に聞こえている。CDではなく、レコードなんだろうなと思わせる音。チェロが海の響き、孕んで鳴り、曲名を知らないことを彼はなんとなく惜しく思った。使い込まれた、味のあるテーブル。板張りの床。 黒いエプロンをかけた女が、水とメニューを持って出てくる。 「いらっしゃいま…………あ?」 あ? 窓から目を逸らして、振り返った。 「あ、」 。 「…?」 「におうまさはるくん!」 硝子が風に吹かれたのか、窓から青い光がチカリと飛び込んだ。塔の上で、なつかしいねと花が歌いだし、勝手にレコードとオルゴールが合奏を始める。花をくれた女の子は変わらないままで、大人になって、そしてきれいだ。 まあるいシルエットの短い髪が、なんとなく、よけいきれいで、彼はすこしだけうろたえた。細い首筋と、襟ぐりの空いた服、鎖骨のラインが白い。黒い目が人懐っこく笑っていて、一瞬言葉にならなかったことが気づかれないようにと気を配るまでもなく、もちろんそれは、面には現れない。 彼女の声に、店主が笑った気配がする。それに彼女が、ちょっと肩を竦めて違う笑い方をした。 昨日の今日で、ほんとうに、という人間の出現はなんとも奇妙な符号を見せる。 塔の上で彼は腕を組んで、成長した女の子を眺めた。まったく10年以上ぶりで、お互いどうしてよくわかったものだ。多分白いはがきと昨日の電話がなかったら、どこか記憶にひっかかっても、お互い気づかなかっただろう。 次に彼女はなんと言うだろう。少し考えをめぐらせる前に、が笑って、コップを机に下ろした。水の影が、白くテーブルに落ちる。 「いらっしゃいませ。」 ふぅわりと笑って、予想した台詞とは違うことを彼女は言った。 「夏の家へようこそ。」 赤い表紙の、メニューが置かれた。白い指先がそれを開いて、一瞬花と見まごう。なんてメルフェンだ。少しばかりスパイスが足りない。窓の外では硝子の中で、相変わらず空と海が交じり合って揺れる。「おすすめはこれ、」と指されたのは今日のランチ・ムニエルさん。変なネーミング。 「いーい魚が入ったとよ。」 笑いながら、歌うような、そんな喋り方をする。じゃあそれを、と注文する自分が、少し遠かった。内心ちょっと、困っていた。塔の上で、鉢植えの花、見下ろして尋ねる。なにから話そう。別段話したいことがあるわけではないのに、そんなことを考えた。 |
>> |