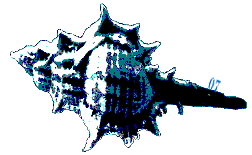 |
ムニエルさんひとつ!と元気な声が遠くで聞こえる。変なネーミングだとは思ったが本当に言うらしい。恥ずかしくないのだろうか。彼はそれにちょっとだけ、ひとりで笑うと海を見た。 寄せて返す波打ち際に、人魚はいない。くまのような店主が、料理をするようで、いそいそと厨房へはいってゆく背中が見えた。あの大きな手で、フライパンや食材を扱うのだろうかと想像すると、よけいにここが絵本の世界のように思えた。 白い浜辺の木の小屋に、青いガラスの球、貝殻の文字、大人になった女の子、くまの店主。彼が作るムニエルなのだから、やはり鮭だったりするのだろうか。 しばらくワルツに耳を傾けると、バターの焦げるいい匂いがしてきた。ちょっと耳に手をやると、もうほとんどピアスの穴は塞がりかけている。 ぐう、とお腹がなる。 窓際はあたたかで、少し眠たくなりそうだ。ワルツの裏っかわに、潮騒が聴こえる。海の呼吸する音。窓辺に置かれた白い貝殻をなんとなく手にとる。白い砂と石を積み上げるように、うずまいた形。内側が空洞なそれには、海の響きが今も反響していると聞く。しかし彼はそれを耳に当てたりはしなかった。ただなんとなく無表情で、弄んでいるだけ。彼の塔に似ている。いびつな螺旋の階段は、渦巻く形に似てはいないか。くるくると回すと、爪先とぶつかって乾いた音を立てる。 「お待たせしました。」 ずいぶんぼんやりしていたような気がする。すっかり夢からさめたような気分がして目を開けた。 目の前に真っ白な皿が置かれて、いいにおい。彼は自分が思った以上に空腹であったことを知る。ムニエルにサラダ、白いご飯。スープ。きちんとした食事だ。どこか素朴で、シンプルな装い。魚は白身であることが、衣と振りかけられたハーブ越しにもわかる。鮭じゃない。少し笑いそうになるのをこらえる。 「…うまそうじゃのぅ。」 思わずお腹がなりそうだ。 「今日はスズキのムニエルです。」 ごゆっくり、と去っていこうとした彼女が、ふとテーブルの上に目を留めてわらった。 「におくん、ええもん持っとぉね。」 「え、」 忘れていた。海で拾ったガラスの瓶だ。集めた貝殻や小石が、たくさん詰まっている。持ったまま入ってきて、少しわすれていたのだ。あんまりこの店に、それが馴染んでいたこともある。 彼女の笑い方は、純粋にこどもが、いいなあとほめるような明るい響きだけで、他にはなにも感じない。だから純粋に、ほめてくれているのだろう。そうかのう、と返す言葉はすこし赤らんで、でも流石は彼の石の塔だ、顔の面には現れもしない。ただなんとなく、いつも通りの飄々とした響きがあるばかり。 少し頬を人差し指で掻いて、それからチラリとを見あげる。彼女は、たくさん集めたとねえ、と感心しているようだ。しきりに瓶を見て、楽しそうにしていた。 「…やる。」 「え?」 言葉が口をついて出た。 「にやるナリ。」 「なり?」 おかしそうに笑って、ありがとうとが頬を緩める。 花びらの手のひらに乗せられた小瓶が、うれしそうに見えて、彼は少し頬を掻いてそれから海のほうに目を逸らした。 |
>> |