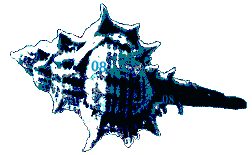 |
食べ終わると、食後には珈琲がついた。 「友達だって言ったら店長がサービス、だって。」 友達だって。小学生のとき、ほんの1年と少しいただけの人間、それからひとつだって連絡も取らず会わずの人間だ。 友達だってさ。塔の上では見えない犬が、ちょっとおどけてふふふと笑う。 おんなじようにうふふと笑いながら、がマグカップを二つもってきた。 香ばしい豆の匂い。スペシャルブレンド、とがなお笑い、どうも、とクマの店主に会釈すると、カウンターでガラスを磨く手をちょっと止めて、くしゃりと笑った。その背中の棚には、ズラリと珈琲豆の入ったガラス瓶が並んでいる。 彼の前に、マグが置かれる。 「はい、どうぞ」 隣のテーブルの椅子をひっぱってきて、も少し、彼のテーブルに近い所に座った。きょとりとして彼がを見ると、「きゅうけいをします。座ってよかですか?」 悪戯する子供みたいにニカリとされた。 「いい職場じゃの、」 思わず彼もニヤリと笑う。 「ほかに客もおらんからね。」 まだ夏も浅い。たしかにぎりぎりシーズンオフと言えるのだろう。そもそもここいらの浜は海水浴場ではないし、地元の小中学生や家族連れが遊ぶ、いわゆる穴場なのだ。だからおそらく海水浴客をあてにするのではなく、地元の人間が夏でも冬でも関係なく通って初めて、成立する店なのだろう。しかしさすがに、日曜の昼時だというのに、空いている―――というより、たしかに彼女の言う通り。彼しかいない。 「ここで働いとるんか?」 「んーん、休みの日とか、暇な時だけ手伝っちょる。普段はねー、町役場のおねーさんしとるんよー」 「なんじゃあ、町役場のおねーさんて。」 「受付事務。」 「公務員がアルバイトなんてしとってええんか。」 「公認じゃけぇ、だいじょうぶ。叔父さんの店やし、それに案外役場って暇なんよ、田舎だけんね。」 なんでも夏、この店が忙しい時期は昼休みにこっそり抜けて手伝いに来るなんてこともできるらしい。 「…ええ職場じゃの、」 今度こそ目を丸くした彼に、が明るい笑い声をたてた。 「そりゃあ、田舎だけんねー」 さっきからそればっかりだ。あっけらかんとして、でも全然嫌な感じはしないな。珈琲をひとくち、たしかにおいしい。 「におくんは今どうしとるん?」 「サラリーマン。」 「東京?」 ことりと首を傾げられて、こくりと頷く。 「東京かぁー!すごいねぇー」 「そうか?」 「首都だよ」 「そりゃそうじゃけど」 きょとりとしてからお互い笑った。大学は関西だったしなぁとが言って、珈琲を啜った。 「こっちにはなにか用事?」 「ばあさん家がある。有給とってちょっくし早めの夏休みなんじゃ。」 「ええね。」 目を細めてが微笑する。さっきからわらってばかりの、まんまるい笑顔だ。変わってない。 「そういえば同窓会の手紙、」 思い出して口にしてみる。 「ああ、あれ。けっこうみんな来たんよー。なんだかんだ、におくんもやけどみんな変わっとらんね、」 ふふ、とおかしそうにが言う。 塔の上でカラフルな旗が、風にはためいて鳴った。空は今やガラスを敷き詰めて、海のようにきらきらと輝いている。 「におくんも来れたらよかったのにねぇ。」 お前も変わっちょらん、なぜだかその言葉は呑み込んだ。 「よぉ俺のこと覚えとったのぅ」 不思議そうにが笑う。 「みんな覚えとったよ。」 嘘だぁ。塔では子犬が笑っている。うそつきに嘘つくなんて、やるなぁ。 「なんでまた、」 「におくんて、なんていうか大人っぽかったやろ。なんでもできたし、その癖よぉサボリよるし、喧嘩も強かったけん。なんか都会から来た転校生、っちゅうてみんな一目置いとったんよ。おしゃれやったしなぁ。」 「…そんなもんただの思い込みじゃ。」 「んふ、そうかもなぁ。だからこそ、みんな大人になって、そういう子供らしい思い込みってあるやろ、そういうのなしで、におくんと話してみたかったんよ。」 思いもかけないことばかり、この地では起きる。大人になった女の子と、むかしばなし、懐かしい少年たちの、新しいはなし。夢だろか。 はなおも話を続けている。窓の外のガラス球。いつか見たような。 ほら、竹中君て覚えとらん?そうそう、ガキ大将の。におくんに投げ飛ばされたん今でも覚えちょって、来たら勝負しちゃろう思うとったのにって笑っとったよ。今?自衛官。さすがに負けるよねぇ。 ガラスが光って、からからとが笑った。本当にどうやら、みんな覚えていたらしい。それに竹中という少年を、覚えていた自分にも彼はこっそり驚いた。 「…覚えとるもんじゃのぅ」 自らにも向けた言葉だった。旗が鳴る。クマの店主が笑っている。ここは夢の世界? 「そ。それにあんなに何回も、屋上まで迎えに行った子、後にも先にもにおくんだけだけんね。」 混乱しかけた彼に、がはっとするような顔でわらった。それはなんだか、内側から白く光っているように見えた。 が飲み干したマグカップを持って立ち上がる。塔の上に風がふわり。どうしたのさ、犬がわらって首を傾げて、花も歌う。彼はなんだか、珈琲飲み終わるのが少し名残惜しいような、そんな気がしている。 |
>> |