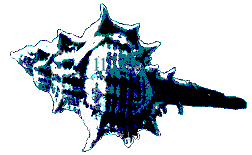 |
その晩彼は夢を見た。 が学校を休んだ。 珍しいこともあるものだ。風邪だそうだ。 いつもお世話になっているのだから、とよくわからない理由で、先生から彼はプリント届ける役目を言い渡された。しかし彼は越してきたばかりで、もちろんの家など知らない。そんなことわかっているだろうに、だいたいの場所を教えられて、「たどり着けるかわからん」と言うと、しかし先生からは不思議な微笑がかえってきた。 『だぁいじょうぶ。すぐわかるけん。』 はてなと首をかしげながらもとりあえず学校を出発し、歩きだした彼は、ここら辺りか、という曲がり角で、すぐに教師のあの、いたずらをたくらんでいるような微笑の理由がわかった。 「…!」 目をまんまるにして、思わず塔から飛び降りた。 と書かれた表札の、家自体は別段なんの変哲もないそこらにありそうな造りをしている。しかしその、庭から覗ける景色の、特殊なこと。 軒に青い硝子の球が、いくつもいくつもぶら下がっている。 風が吹くと、カリチ、カチリ。風鈴とは違う、もっと重たい音を立てる。光と影のブルーが揺れて、不思議な空間が出来上がっていた。カチリ、カチリ。心臓の鼓動にも似た、けれど不規則なリズム。ゆらゆらと、海の水か空の青が、カーテンのように軒を覆っている。すごいね、と犬が隣でぽつり、尾を振った。 どれくらい見つめていただろう。 ふいに二階の窓がカラリと開いた。 「におくん?」 だ。 窓から顔を出して、きょとりと彼を見下ろしている。少しばつが悪そうに、彼は頭を掻くと「…おう。」とだけ言った。 「どげんしたと?」 「…学校、プリント。」 それだけの単語でも、ああ、とは合点がいったようで、「ちょー待っっとって〜!」窓から顔が引っ込んだ。パジャマだったな。ちょっと考えて、当然だろう、なにせ風邪で学校を休んでいるのだから眠っていたに違いない。 じきに玄関が開いて、パジャマの上にカーディガンをあわててひっかけただけのが飛び出してきた。。 「わわ、ごめんね、ありがとう〜!」 「…ん。これ、宿題。」 「げ、いっぱい…。」 先生から預かったプリントの束と、それから女子から預かった手紙を渡した。にこにと受け取るを見ながら、女子ってめんどうな生き物だなと少し考える。用は済んだ、しかし話しながら、それでもどうしても、自然にガラス球に彼の目がいく。玄関からでも、青い光がちらちら見える。 「…、」 きょとんと彼の落ち着かない視線の先を追っかけて気がついて、も笑った。 「すごかろ?」 黙って彼は頷いた。確かにすごい。 「叔父さんが作ったとばい。」 そう満面の笑顔で言いながら、あ、と何か思いついたようにがパチリと手をたたいた。 「におくん、こっち!」 そのままぐいぐいと庭へひっぱられる。手が熱い。熱があるのだ。寝てたほうがいいとか、もうかえるとか、なにも言えず、言われるままに縁側に座らされて、「ほら、」そこは海の底だった。 ちょうど太陽がガラスの向こう。きらきらきらと真っ青な光と影。 「…すごい、」 言おうとしたこと、すべて吹っ飛んでしまった。ぽかんとしたままの彼を見ながら、がにおくんがびっくりしとる、とおもしろそうに笑ったけれど、そんなのすら今の彼には気にならなかった。まっさお、まっさおだ。塔も現実も、今彼の中にはない。ただ目の前に広がる、海と空の青、閉じ込めたガラス玉だけ、確かにある。 しばらくして、見ててええよ、とが笑って部屋へ戻っていったのにも彼は気がつかなかった。。 「あれ?」 知らない男の声に、彼がビクリと肩を震わせると、あたりはすっかり日が暮れて、空が真っ青。ずいぶん時間が経ったようだ。 肩から鞄を引っかけた男の人が、めずらしそうに彼を見下ろしている。 「めずらしかな。の友達てや?」 「…クラスが一緒で、プリント、持ってきただけじゃ。」 その返事にそうかぁ、と男は笑って、ぐりぐりと彼の頭をなでた。 「ありがとなぁ。」 なにぶん突然のことで、防御が遅れた。目を丸くして固まった彼に、男がおかしそうに笑う。なんとなくに笑い方が似てた。何も言えず、彼の眼はそのまままた自然と、ガラス球に移る。 「ずっと見とったんか?」 こくりと頷く。それをどう思ったのか、男は少し、頭を掻いて首をひねった。困ったような、照れているような、笑いだしたいのこらえているような、そういう表情をしていた。 「…そぎゃん気に入ったつなら、持って帰るね?」 「え、」 思いもかけない言葉だった。顔をぱっと明るくして、彼はまだ若い男を見上げた。その顔は、持って帰っていいよ、と心から言っているように見える。 しかしその顔は次第にしゅんと曇り、それもすぐに消え、大人びた表情になる。石で積んだ塔が、彼の中にかえってきた。犬も隣で吠える。 彼のそのずいぶん大人びた顔は、男を内心少し驚かせていた。男の姪とは、まったく違う生き物に思えたのだ。彼は少し唇を噛んで、しかし次の瞬間には飄々とした普段の"なにも気にしてない"顔に戻ると男を見上げた。 「………いい。」 いらない、と言った。 「そう?」 男が、先ほどのぱっと明るくなった彼の顔を思い浮かべてか、遠慮したと思ったか、首を傾げる。 「…引っ越すとき、」 邪魔になるからとは言いたくなかった。 「壊したら嫌だけん。」 「引っ越すと?」 男が目を丸くする。 「多分そのうち。」 彼の複雑な事情を、わざわざ説明する気はない。犬がきゃんと吠えた。こういうときだけ、人間の言葉をしゃべらないんだから。彼は引っ越すとき、きっとこの青いガラス球は割れてしまうだろうと思った。ずっと抱えていれば、母に「邪魔になるから置いて手伝いなさい。」といわれると思った。 「…そぎゃんとね。残念ばい。」 2年以上同じ土地にいたことがない。彼は思わず、ひとりごとのように言った。言ってから、なんとも言えず、彼は黙った。しまったと思った。青い光と影の中に、彼はぽつりとひとりだった。 「これ作るのな、もう止めようち思っとったつたい。」 どれくらい二人とも黙っていただろう。 ふいにそんな言葉が男の口から出た。え、と顔をあげた。その顔は彼自身が思うよりもすっと、がっかりした素直な表情になっていた。 男は思いもかけない明るい表情で笑うと、「でもやめた。」その頭に手を乗せた。 頭に乗せられた大きな手を、目をまんまるにして彼は見上げる。 「また作っけん、大人んなったら取りにきたらよかよ。」 持って帰れんごつ、たっくさんつくっとてやるばい。とおんなじ笑顔だ。ふいにその顔がクマになる。ガオウ。 朝の光。 「・・・思い出した、」 あのあと暗くなってからようやっと家へ帰りついた彼は、見事に風邪をひいたのだ。おかげであの感動も、すっかり忘れてしまっていた。 軒にぶら下がった、ガラス球を見る。真っ青な光と影。いつか見たまま。そのままの色。 忘れているうちに、彼はかえってきて、そして約束通り、ガラス球、もらってしまった。しかも覚えていなかったのは彼ばかり。なんだかこれは。 「…悔しいのう。」 僕覚えてたよ、こういうときだけ、人間の言葉、話すんだから。犬が笑った。 |
>> |